***
まるで自分自身がヒロインになったかのような経験を、人生の中で誰でも一度は経験するだろう――。
私も、その一人だった。
物心ついた時から高校に入った頃まで、私は周りの大人からは可愛がられ、友達からも慕われたことで、こうしたいと思ったことはだいたい叶えられた。
まるでこの世界は私が願った通りに叶う、都合の良い世界だった。
だから、私は自分自身をこの世界のヒロインのように思っていた。
けれど、時が進み、社会を経験していく内に、『私』という人間は物語の端役に過ぎないことを悟る。否、むしろただの我が儘な女に成り下がっていた。
私はお姫様ではない。
この世界には、私のピンチに駆け付けてくれるヒーローも、私を迎えに来てくれる白馬の王子様も、辛いときに寄り添ってくれるカッコイイ幼馴染も、願いを分かってプレゼントを届けてくれるサンタクロースも、いない。
少し容姿が整っていたために周りからチヤホヤされたことで、私は勘違いしていたのだ。
自分がやりたいことやしてほしいことだけを言えば、周りからの反感を生む。
現実を知った私は、周りから疎まれないように、上手く適応しながら生きることを心掛けた。
無理難題を言わない。否定しない。現実的に物事を考える。頼みごとをされたら必ず受け入れる。人と話している時に自分の話をするのは、九対一くらいの割合がちょうどいい。
私の幼少期を知っている人からしたら、私の変わりように驚くことだろう。
しかし、それくらい徹底的にやらなければ、自分を主人公のようだと勘違いしていた傍若無人な私には日常生活は送れない。
誰かに我が儘を言うことがなくなった私は、気付けば社会人になっていた。
大人に成長した私が選んだ道は――、
「――のぞみ先生!」
ボーっと机の上の書類に向き合っていたら、私の名前を呼ぶ声が聞こえた。
横を見ると、私が受け持つ五年一組の児童である杏奈がいた。杏奈の手には、先ほど返したテストの解答用紙が握られていた。
私と視線が合った杏奈は、満面の笑みを浮かべて一歩分だけ私の近くに寄った。私が何をして欲しいのか分かるでしょ、そう言わんばかりの仕草に、くすりと笑う。
「今回のテストで百点だったのは、杏奈ちゃんだけだよ。すごい!」
放課後の職員室で、まだ自分自身の可能性を信じている少女の頭を優しく撫でた。
――現実主義者になった私が選んだ道は、小学校の先生だった。
<――②へ続く>
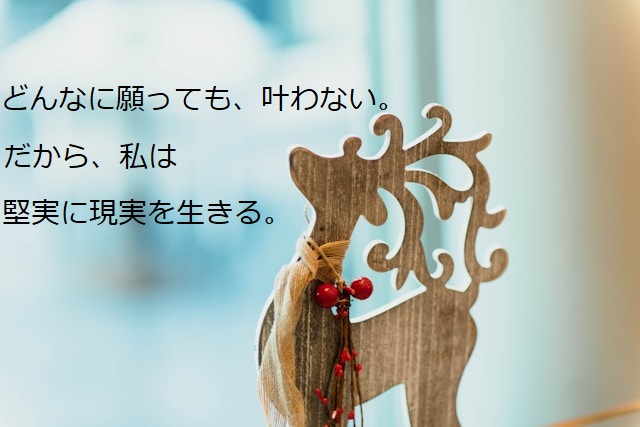


コメント