・石と風①
・石と風②
・石と風③
***
初対面の人と二人きりで話すなんて、なかなかにハードルが高い。先ほどまでは吉内さんが仲介に入ってくれていたが、それも瞬間のことで、すぐに他のママさんたちの元へと足を向けてしまった。吉内さんは気遣いが出来る人だと思った評価は、すぐさま覆すことになった。
グラウンドを見下ろせる位置で、わたしは高垣さんと並んでいる。
一応、わたしの横にいる高垣さんは、このチームの監督だ。それなのに、何も指示せず、私なんかといていいのだろうか。
だけど、グラウンドを見下ろす高垣さんの横顔からは、信頼の色が滲み出ていた。
「あの……、いつも累がお世話になってます」
沈黙を打ち破るように無難な言葉を口にすると、高垣さんはグラウンドから私の方に視線を向けた。高垣さんの眼差しは、わたしにとって少しだけ眩しい。
「累、迷惑かけていませんか?」
「いやいや、迷惑なんてとんでもない。むしろ累ちゃんがいなかったら、このチームは今みたいな大進撃は起こせていないですよ」
今までは大きな大会ではベスト16が限界だったのに、累が四番でエースを務めるようになってから表彰台を狙うことが出来るようになった――、そう高垣さんは、声高らかに語ってくれる。
「累ちゃんはすごいです。いつもの練習で身に着けた実力と、ハッキリと迷いのないプレーで、皆を引っ張ってくれる。でも、累ちゃんの本当にすごいところって、運動神経が優れているとかじゃなくて、どんな状況でも笑顔で乗り切るところなんですよね」
あ、分かる。
累は目の前のことを何でも楽しんで取り組むことが出来る。
勉強に関しても、親であるわたしたちが何かを言う前に、自分で自主的に取り掛かる。逆に心配になって一度累に聞いてみたら、「知らないことを知れるのは楽しい。どんどん自分が変わっていくのは、嬉しい」、と言っていた。
野球に対しても、累は同じ気持ちを抱いているのだろう。
「累ちゃんが諦めていないなら、まだまだこのチームは終わっていない。みんなそう思って、自分の実力以上の力を発揮してしまうんです。累ちゃんのおかげで、チームの実力は底上げされていますよ。いるだけで感化されるのは、川澄さんとそっくりです」
まさかここでおとうさんの名前が出るとは思わず、「おと……父、ですか?」とオウム返しをしてしまった。
「監督に赴任する前、川澄さんの跡を引き継ぐために、川澄さんがこのチームを導いているところを見たことがあるんです。川澄さんは終始声を荒げることなく、和やかに練習を進めていきました。川澄さんがすることといえば、大まかな練習方法の提示と、子供たちの行動を全力で褒め称えること。それだけなのに、子供たちはがむしゃらに練習に取り組むんです。それは、現役時代に仏の川澄と呼ばれていた時と同様のことを、子供にもしてあげられるということです。どの立場だとしても変わらない川澄さんを見て、改めて人としての器のでかさを思い知りましたよ」
「父って、そんなに凄かったんですか?」
「すごいなんてもんじゃない! 川澄さんは現役時代から、ずっとずっと素晴らしい方です!」
高垣さんは鼻息荒く、目を光らせた。たったそれだけで、高垣さんがおとうさんのファンだったことが伝わって来る。
「現役時代、他の選手とは群を抜いて優れた選手だったのに、川澄さんは一度も鼻につくようなことはしませんでした。チームメイトに対してだけでなく、相手選手やファンの人に対して、いつも誠実に対応していました。オーバーワークで体を壊してしまい、プロの監督を担った時も、監督を降りてコーチになって裏方で日の目を浴びなくなったとしても、川澄さんの振る舞いは何も変わらなかった。子供たちと接している時も、そう。今だって、世界に飛び出して、同じことをしているでしょうね。誰に対しても誠実に接する川澄さんだからこそ、彼の周りは、いつも本当に楽しそうだった」
娘という立場で誰よりもおとうさんの近くにいたのに、わたしは知らなかった。怪我によって今までの努力が無駄になってしまった、というレッテルでしか、わたしはおとうさんのことを見ていなかったのだ。
それ以上を知ろうとはしなかった。
だから、プロ野球選手を怪我で引退して、監督やコーチなど別の立場になった時も、ただ強がっているだけだと思っていた。違った。おとうさんは本当に全てを楽しんでいたのだ。
「このチームは、間違いなく川澄さんが作ったチームだ。川澄さんの人柄が伝わって、みんな自ら野球を楽しくしている。だから僕は、川澄さんが築き上げた土台を崩すことなく、子供たちがのびのびとプレーできるように支えるだけです」
ここにきて、ようやく高垣さんがグラウンドに立たずに、わたしと話してくれる理由が分かった。
高垣さんは、子供たちのことを全面的に信じているのだ。高垣さんは自身の役目を、子供たちが危ないときに手を差し伸べるくらいにしか思っていない。
そして、それはおとうさんがやって来たことでもある。
「知らなかったです」
そう正直に言うと、高垣さんはふにゃっと笑った。
「自分がして来たことは、自分では言いにくいものですから。だから、知っている周りの人がちゃんと言葉にしてあげないといけないし、引き出す環境を作ってあげないといけない、って僕は思います」
わたしはただ小さく頷くだけだった。
「差し出がましいことを言ってしまったら申し訳ないですが、累ちゃんのお話聞いてあげてください。累ちゃん、本当に頑張ってるんで。誰よりも早くグラウンドに来て、一人でグラウンドを整備して、練習するんです。誰よりも疲れてるはずなのに、笑顔を絶やすことなく練習に励む。一人の人として尊敬します、本当に」
四番でエース。
その肩書を持っていることだけしか、わたしは知らない。累がどのような努力を重ねて、どのような気持ちでいるのか、母親なのに知らない。
努力、や、才能、といった簡単な言葉で、わたしは累のことを一括りで考えてしまっていた。
いつもそうだ。わたしは表面的に全てのことを見てしまう。
「旦那さんにもよろしくお伝えください。いつも差し入れ助かってます、って」
「はい……、は? 差し入れ……?」
高垣さんの言葉に、一オクターブ高い余所行きのわたしはいなくなった。
「毎週日曜日に大量のスポーツドリンクを買って来て、子供たちにあげてくださいって、僕に渡すんです。ぜひ子供たちに声かけてください、って言うと、すごく謙遜されながら帰って行かれるんです。そんなシャイにならなくていいのに」
傑の姿は、容易に想像出来た。
そして、言葉通りに家へ帰ることはせず、どこに向かうのかも。
「すみません、ちょっと用事を思い出したので帰ります」
「長話になってしまいましたよね。よかったら、また来てください」
「はい、ぜひ。累のこと、引き続きよろしくお願いします」
そう頭を下げると、私は歩き始めた。
今日、わたしがグラウンドまで来た理由は、累の活躍を見るためだった。
一番近くから累の姿を見ることは出来なかったけれど、遠目からでも累が頑張っていることは伝わって来た。何よりも高垣さんと話したことで、累のことも、予想だにしていなかったおとうさんのことも、知ることが出来た。
多分このままグラウンドまで行って、累を見ようとしても、累の全てを知ることは出来ない。もし、本当に累の活躍を目に収めたいのなら、累が家を出た瞬間から見守る必要がある。
だから、今日はこれでいい。
それより、今は何よりも優先して行かなければいけない場所が出来てしまった。
「――やっぱりね」
グラウンドから少し離れた場所で、傑は芝生の上で寝そべっていた。
<――⑤へ続く>
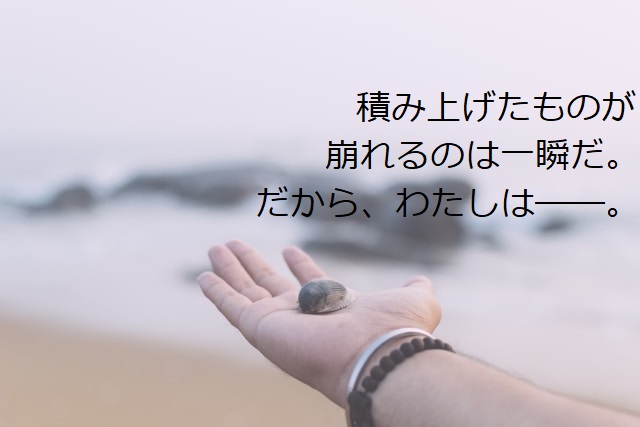



コメント