・石と風①
・石と風②
・石と風③
・石と風④
***
傑を考える時、一番初めに思い浮かぶのは、リビングのソファでうつ伏せになってスマホを触る怠け切った背中だ。
付き合っていた時は、ちゃんと格好いい姿が浮かんでいた。人と仲良く接している姿、周りにささやかな気配りが出来る姿、いつまでも一緒にいたいと思わせる柔らかな雰囲気。好青年という言葉が、わたしの中でピタリと当てはまっていた。
だけど、結婚して累が産まれてから、わたしの中の傑は変わっていった。
身内には、とことん怠け切ったところを見せる。優柔不断で、自分から何かを決めることはない。目立つような真似は避けて、常に中立を心掛ける。
いつの間にかダメな部分ばかりが目に入ってしまうようになっていた。
そんな傑の頼りない背中を思う度に、わたしは思ってしまう。
――累のおとうさんなんだからしっかりしてよ、と。
「やっぱり、ここにいると思った」
心地よく目を閉じていた傑を覗き込むようにしながら、わたしは声を掛ける。大きく目を見開いた傑は、「……捺貴」とわたしの名前を呼んだ。
傑の隣に腰を下ろすと、傑も体を起こす。
柔らかな風が芝生を撫でると同時、軽快な金属音とはしゃぐような声が聞こえた。
「昔から変わらないよね、傑って。自分がやったこと、もっとアピールすればいいのに」
「俺がそういうの苦手だって分かってるのに、よく言うよ」
微苦笑を漏らす傑に、わたしは出会った時の傑を思い出した。
自分のことを開けっぴろげに語ることはせず、自分の手柄などないかのように振る舞っていて。だけど、人がやったことは、まるで自分のことのように全力で褒めてくれる。
傑は今も昔も変わっていない。
変わったように思ったのは、わたしの見方が変わったからだ。
傑に、傑以上のことを求めるようになっていた。父親らしい振る舞い、頼りがいのあるおとうさんとして振る舞ってほしいという思いが強くなってしまった。
「ごめんね」
傑に聞こえないような声量で、わたしは自分の身勝手さを悔いる。
傑にだけ変化を求めることは、ある種の責任転嫁だ。
傑におとうさんとしての姿を求めるということは、わたし自身も累のおかあさんなんだからしっかりしないと、ということになる。それは出来なかった。だから、何も言葉にせず、一人で身勝手な不満だけを抱いていた。
元より努力することが苦手なわたしと傑。このままではよくないと思いながら、お互いに深く干渉することはなく、このままでいることを選んだ。
だって、その方が楽だから。傷付けることも、傷付くこともなく、無難な家庭を築き上げることが出来る。
ちゃんとした親になるということが、どういうことか十年経っても良く分かっていない。
だけど、傑はいつの間にか一人でこっそりと変わろうとしていた。誰よりも一番近くにいたのに、わたしは傑の変化に気付けなかった。
ふっと息を吐く音が隣から聞こえた。
「俺さ、お義父さんのファンなんだ」
思ってもいない傑の唐突な告白に、「へ?」という間の抜けた声が漏れた。
「川澄選手のファンなんだ、って言ったの」
「なに急に? そんなこと一度も聞いたことないよ」
そもそもの話、傑が野球ファンだってことも知らなかった。
「だって、言ってないもん」
悪戯っ子のような純粋な笑みを浮かべる。
「だからさ、捺貴と結婚する時に、お義父さんとお義母さんに挨拶行ってマジでビビった。あの川澄さんが俺の前にいるって!」
「私の苗字で気付かなかったの?」
「うん、まぁ、妄想はしたよ。川澄捺貴のお義父さんが、あの川澄さんだったら面白いなって。でも、本当にそうなるって思わないじゃん」
それもそうか、とわたしは一人納得する。有名人と一般人は住む世界が違う、と心のどこかで常に一線を引いていて、まさか交わるようになるとは夢にも思わないだろう。
「でもさ、目の前にいるお義父さんは、俺が知ってる川澄選手その人だった。テレビで見ていた時と何も変わってないんだな。お義父さんは、俺みたいに上っ面な奴にも優しかった。お義父さんみたいにすごいこと出来てなくても、会う度に俺のこと心配してくれるのが嬉しかった」
「プロ野球選手じゃなくなってたのに……?」
「立場なんて関係ないよ。ファンになったキッカケは確かにプロ野球選手だったからかもしれないけど、川澄選手の人柄を尊敬していたんだから。プロ野球選手だったとしても、監督だったとしても、ただのお義父さんだとしても、変わらない」
ありのままのおとうさんでも好きだ、と傑は言ってくれる。それは、わたしが気付かなかっただけで、おとうさんが積み重ねて来た努力がずっとずっと残っているということだ。
「でさ、お義父さんたちが世界に旅立つって聞いた時、お義父さんに打ち明けたんだ。ファンになったキッカケを」
小学校二年の時、傑は家族で球場まで遊びに来た。けれど、傑はそこで迷子になってしまった。そんな時、試合前だったおとうさんが傑を見つけて、そばにいてくれた。合流できるまで、ずっと傑の手を握っていて、不安にならないように色々な話をしたらしい。そして、無事に両親と合流出来て、おとうさんの手を離した時、「ホームラン打ってね!」と子供ながらに言った。子供にとってはただの応援のように思えても、プロ野球選手からしたらただのプレッシャーの他ならない。けれど、実際におとうさんはホームランを打った。それから、傑はおとうさんのファンになったようだ。
傑は「結婚を報告するより緊張したかも」とカラカラと笑う。
「おとうさんは、なんて……?」
「憶えていたんだ。俺が忘れてるような話まで、全部憶えていてくれてた。あの時の子供が、あんなに大きくなったんだなって笑ってくれた」
空を見つめる傑の目は、まさに少年のようにキラキラと輝いている。
「でさ、なんていうのかな。俺ももうちょっと向き合いたいって思った。累にも、捺貴にも、色んなこと全部に。胸を張れる自分になってみたくなった。でも、俺って努力が似合わないじゃん。昔からずっとこっそりしてたから、今更になってあからさまが少し恥ずかしいっていうか。だから、こうしてバレないようにちょっとずつ変わっていこうと思ったんだけど――」
「見つけちゃったわけだ」
「あーあ、高垣さんにも口止めすればよかった」
そう言うと、傑はそのまま芝生に倒れ込んだ。
傑も同じだと思っていた。
だけど、傑は傑なりに考えて、不器用にでも親という使命を全うしようとしていた。その一環として、累に気付かれないようにさりげなく累を支え始めた。
わたしは目に見えることだけしか知ろうとしなかった。
おとうさんのことも、傑のことも、表面的に見て勝手に決めつけていた。
だから、おとうさんに対しては努力を活かす場がなくなって無駄になったと思ってしまったし、何もしようとしない傑を見て今更頑張っても無駄だと思ってしまった。
だけど、実際は違う。
おとうさんが重ねて来た努力はずっと活かされ続けているし、傑がしている努力も誰かの役に立っている。
やればやるだけ、実は結ぶのだ。
わたしも傑に倣って、背中から芝生に倒れ込む。夕焼けが眩しい。わたしは夕焼けから目をそらし、傑を見た。
「ねぇ、もう少しここにいない?」
「だな」
わたしたちは特に言葉を交わすでもなかった。でも、言葉にしなくても、お互いの意志は伝わっていた。ただ心地よい空気だけが、わたしたちの間に流れている。
「あれ?」
毎日毎日聞いている声が、私たちの耳に届く。その声に体を起こすと、
「二人とも、こんなところで何をしてるの?
」
バットとグローブを持って、いかにも野球少年みたいな格好をしたわたし達の愛しい娘が、キョトンと首を傾げて立っていた。
「累を待ってたんだ」
「一緒に帰ろうか」
「……珍しいね」
累は不思議そうに言ったけど、その顔に嫌気はない。
累を真ん中にして、わたしたち家族は並んで歩き出す。
三人並んで歩く姿は、他の人にはどう見えているのだろう。仲のいい家族だと見えているのだろうか。
横を見ると、累は笑顔で歩いていた。
いつまで続くか分からない光景を前にして、わたしはもっと早くこうしていれば良かったと思った。
累の頭上の上で、傑と視線が重なった。傑の言いたいことは分かっている。わたしは首を横に振り、そして縦に振った。
わたしが累に言う。
ううん、言いたい。
「ねぇ、累。野球は楽しい?」
「言わないで」
「……え?」
急に立ち止まった累は、地面をじっと見つめている。
「おかあさんが言おうとしてること、分かるよ」
累は頭がいい。どうやら私のたった一つの質問で全てを察してしまったようだ。
「わたし、女の子だってこと。だから、いつかは今みたいに野球をすることが出来なくなるって。無駄な時間を過ごしてるだけだって」
声を上げていないけれど、累は泣いている。
累は子供だけど、同年代の子供よりも成長しているのだとずっと思っていた。けれど、それはわたしがちゃんと向き合っていなかっただけだ。累は大人への階段を踏み始めているけど、まだまだ子供のままなのだ。
「でもね、わたしは今が楽しいの。キャッチャーミットにボールの届く音が好き。バッドにボールが当たって、目いっぱい遠くまで飛ばす感覚が好き。みんなと一つになって相手に勝つ時が、好き」
累の言葉で、どれだけ累が野球を楽しんでやっているかが伝わって来る。
「今やっていることが、無駄なことになるって分かってるよ。ちゃんと分かってる。けど、それでもわたしは――」
「無駄になんてならないよ」
傑が累の言葉を遮って言う。
累の視線も、わたしの視線も、傑へと注がれる。昔よく見た優しく穏やかな笑顔が、いや昔よりも少しだけ大人になって安心感の増した笑みが、そこにはあった。
「累がして来たことは、累の力になって、いつか累が困った時に助けてくれる」
ここまで傑がハッキリと言葉にするところを見るのは初めてだった。
いつもは波風立たないような言葉を選び、自分で責任を取ることを選ばない。それなのに、我が娘のためを思って、傑は強く言葉を言う。
「たとえ累が野球をやらなくなって、別のことに夢中になったとしても、絶対に」
気付けば、「おとうさんの言う通りよ、累」とわたしも言葉を挟んでいた。
「累の努力は絶対に無駄にならない。だって」
――わたしの持論は、『努力なんて意味がない』。
だけど、そうじゃないことが今日覆された。
努力して来たことが崩れることなんて、誰の身にも訪れる。順風満帆に人生を歩める人なんていないだろう。それでも、行なって来た努力がすべて無駄になることはなく、次のことに受け継がれる。受け継がれて、積み重なって、そして、然るべきところで、今までの行ない全てが報われるようになる。
きっと人生はそういう風になっている。
「だって、今も誰よりも頑張ってるんでしょ? わたし、累のお話聞きたいな」
「うんっ!」
眦に涙を滲ませながらも、累は弾けるような笑顔を見せた。
「よし、今日は累の好きな物作っちゃうよ。唐揚げにする?」
「え? いつもは準備が大変だからって作ってくれないのに? 本当?」
累の言う通り、いつもの食事は適当に作り易いものを作って終わらせる。
でも、この笑顔がいつまでも続くなら、料理の手間なんて本当に何でもないことだ。
だから、今はちゃんと手を加える努力をしたい。
そして、累が、傑が、わたしが、皆が喜ぶ食卓を作り上げたかった。
<――終わり>
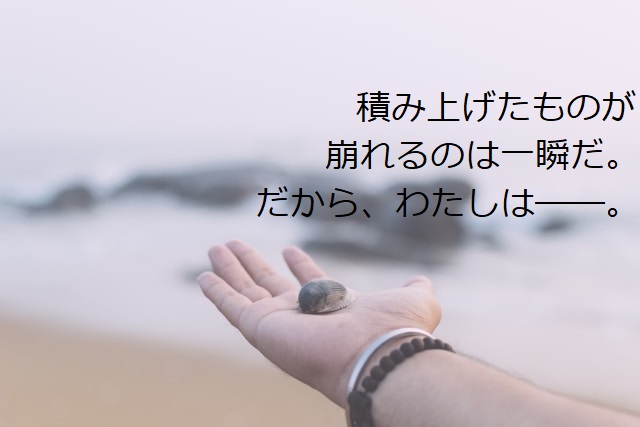



コメント