・石と風①
・石と風②
***
オリンピックだったり、夏の甲子園だったり、そういったスポーツ中継を見る度に思う。
この人達は自分の才能を的確に把握し、適切な努力を惜しみなく注いだ、ダイヤモンドそのものだ――、と。
人には誰しも何かしらの才能があると思う。けれど、才能を伸ばすためには努力は最低条件だ。それも、ただがむしゃらな努力ではなく、方向が見合った努力が必要になる。
たとえば、味覚音痴な人が料理の道を極めようと努力しても、周りの求める至高の味を知ることは叶わないから、料理に費やした時間は無駄になってしまう。一方で、舌が優れている人が料理の道を極めることは、理にかなっているから、持っている才能をフル活用して誰からも認められて有名店を築くことが出来るというものだ。
自分の子供という色眼鏡を除いても、累には才能があると思う。順当に努力をしていれば、累も表舞台に立つことが出来るだろう。
けれど、累は才能に見合わない努力を重ねてしまっている。
累が今没頭しているのは、野球だ。野球が上手くなるために、日夜練習に励み、その努力の対価として四番でエースを任されている。
大役を任された累は、これから益々野球に注力していく。――累が現実に打ちのめされて、積み上げた努力が水の泡と化してしまうまで。
累は、女の子だ。
今はまだ周りの男の子たちと身体的な差はないかもしれないが、これから必ず男女の差が生じる。男の子たちはメキメキと体を成長させ筋肉も増し加わって来るのに、累は逆に柔らかな体になっていく。
累が必死に努力して到達した領域に、同級生たちは累よりも少ない努力で辿り着く。むしろ、もっともっと突き放されることだってある。
男女差ゆえの当然の事象、到底努力ではカバー出来ない領域だ。
そうなった時、誰よりも苦しむのは累だ。
しかも、現時点で周りのチームメイトよりも才能があって努力を重ねている分、崩れ落ちた時の衝撃は大きいだろう。
累は全てに諦めを抱き、夢も希望もなく、ただ日々をこなすだけの人生になってしまうかもしれない。
そもそもの話、女性のプロ野球は、まだ男性のプロ野球のようにメジャーではない。テレビに取り上げられることも少ないし、オリンピックのような世界規模の注目を集めることも日本では珍しい。もし今のまま野球の才能に秀でていたとしても、やっぱり累はどこかで妥協というか限界を迎えてしまうのだ。
累には私のようになって欲しくなかった。
だから、早めに方向転換をして欲しいと思うのだけれども。
「わたしに言う勇気はないのよね」
今までなぁなぁに接して来たくせに、今更どの口が言えるのだろう。
だけど、その責任を夫の傑に押し付けようとしているのだから、わたしはきっとズルい人間なのだ。
「……はぁ」
日曜日の昼下がり。一人で家にいると、否が応でも色んな事が頭を巡ってしまうというものだ。
累は野球チームに足を運び、傑は日曜日になると、よく家を空ける。行き先は知らない。
普段から時短を意識して簡単な料理しか作らないけれど、わたし一人のためだと思うと日曜日の昼はカップラーメンになってしまう。
「これはこれで美味しいからいいけどね」
ズズズッとラーメンを啜ると、化学調味料の味がわたしの舌を刺激する。
結局、昨日の傑との話し合いはなぁなぁのままで終わり、累をどうするかは決め切ることが出来なかった。
積み上げて、積み上げて、積み上げた結果。膨大な血と涙と時間を注いだにも関わらず、努力が崩れ、水泡と帰す瞬間はどれだけ虚しいだろうか。
おとうさんの努力が崩れる瞬間を、わたしは何度も見て来た。
だから、早ければ早い方がいい。
そうしたら、累だって新たな道を見つけるのが早くなり、その分適切なものに才能を注ぐことが出来る。
「あれ」
カップラーメンの器が気付けば、空になっている。
傑と累が帰って来る前に、後片付けをしなければ。立ち上がると、わたしはビニール袋に容器を入れて縛る。そして、部屋にカップラーメンの匂いが籠らないように窓を開ける。
心地よい風が部屋に入って来た。
わたし達一家が住むのは、十階建てマンションの七階だ。だから、窓辺に立てば、広範囲の景色を見ることが出来る。
そこでわたしの目が捉えたのは、累が所属する野球チームが土日で練習しているグラウンドだった。普段だったら特別に意識することがないグラウンドだけど、昨日の傑とのやり取りもあって、わたしの目はグラウンドに釘付けになっていた。
グラウンドの上では、点のように小さな人影がしきりなしに動いている。あそこで累は活躍しているのだろうか。
でも、それもいつか終わりが来る時間だ。男の子のように気が済むまで白球を追いかけることは出来ない。
いつ終わりが来るか、どのように終わりが来るか。それは誰にも分からない。
「もしかしたら、わたしの役目かもしれないのよね」
累に野球を終わらせることがわたしになる可能性を考えると、少しだけ怖ろしくなった。
それと同時、わたしはほとんど累の活躍を目にしていなかったことに思い至る。
この後のわたしの予定は、ダラダラと動画を見て過ごすつもりだ。いわゆる、ただの暇つぶし。
だけど、ほとんど顔を出していないのに、今更になって累の様子を見に行くというのは周りからどう思われるだろう。それに、この炎天下の中だ。普段外に出ることを渋っているわたしが出てしまったら、すぐに暑さにやられてしまうだろう。
だから、家にいることが得策だ。
「部屋で見るよりも、何百倍も暑いわ……」
頭では分かっていたのに、わたしは何故か家の外に出てしまっていた。
右手には日傘、左手にはハンディファン、首にはひんやりとしたタオル。万全の暑さ対策をしたはずなのに、襲い掛かる暑さは尋常ではなかった。
「……でも」
わたしがずっとエアコンの利いた涼しい部屋でゴロゴロとしている間、累はこんなにも暑い状況で頑張っていたのだ。しかも、四番でエースとしっかりと成績を残している。
累は、わたしが思っている以上にすごい子なのかもしれない。
そんな累を待ち受ける結末を思うと、少しだけ、いいや、かなり心が痛んだ。
性別なんて絶対に選ぶことは出来ないけれど、どうしてわたしは累を男の子として産んであげなかったのだろう。
残暑もあってか、そんなことに頭を悩ませていると、わたしの耳に豪快な金属音が響き渡った。追随するように、歓声も上がる。
グラウンドまで、もうすぐそこまで近付いていた。累のプレーする姿を、この目でしっかりと見ることが出来る。なのに、私の足は竦んでいた。
活躍する累を見て、私はどういう感情を抱くのだろう。母親として抱くべき真っ当な感情を抱ける自信は、どこにもなかった。
引き返すなら、今しかない。
「……あ」
そう思っていたら、私の目は二人の男女の人影を捉えてしまった。
女性の方は、累のクラスメイトの咲都くんのお母さんで、確か苗字は吉内さんだ。隣にいる男性は、残念ながら見覚えがなかった。
と、そこまで記憶を振り絞ったところで、吉内さんと目が合った。
吉内さんが無邪気に手を振ってくれたので、わたしは無視をするわけにはいかず、会釈を交えながら二人に近付いていく。完全に帰るタイミングを逃してしまった。
「こちら平石さん。累ちゃんのお母さんで、前の監督の川澄さんの娘さんでもあるんですよ。で、こちらが高垣さん。川澄さんの後を継いで、今のチームの監督をしているの」
気遣いできる人なのか、吉内さんはわたしと高垣と名乗った現監督の橋渡しのような役割をしてくれた。
「ああ、あなたが」
ハッとしたような表情を浮かべた高垣さんだったが、
「いつかずっと挨拶したいと思っていたんです」
すぐに友好的なものへと切り替わっていった。
<――④へ続く>
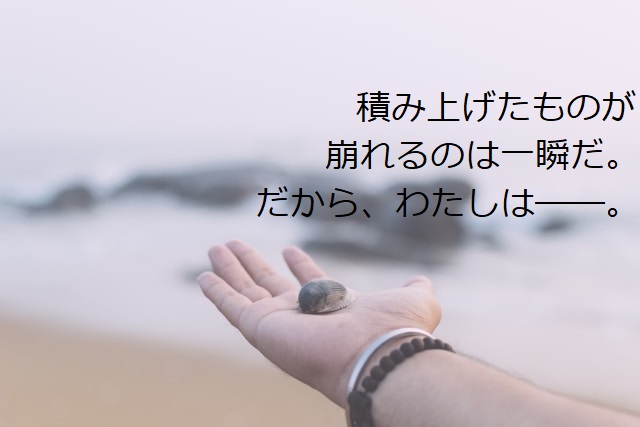



コメント