・石と風①
***
――人生で一番頑張ったことは?
そう聞かれたら、わたしは胸を張って「今だ」と答えたい。
わたしの生活リズムは、だいたい決まっている。
早朝に目を覚ますと、家の家事をこなしたり、傑の弁当を作ったり、累が学校へ行く準備を手伝ったりする。傑と累が家を出ると、残っていた家事を片付け、わたし自身もパートへ行くための用意をする。日中はパートに時間を当て、夕方前に家に帰るなり、また夜ご飯を作ったり掃除をしたりと、家事をする。
それを毎日毎日続けている。
正直、現世で生きる人は誰もが行なわなければいけないことだって分かっている。分かってはいる上で、わたしはいつも誰かにわたしのことを褒めて欲しかった。
わたしみたいな怠慢な人間が、傑と結婚して十二年、累が産まれてから十年も続けられていることが奇跡に近い。
これがわたしに出来る最大級の努力だ。しかも、負担にならないように、所どころ手を抜いている。
今以上に求められてしまったら、私は全てを投げ捨てて逃げ出す。実際直面したとしたら、行動に移せるかはあえて言葉にしない。
「ただいま」
玄関先から累の声が聞こえて、もうそんな時間かと思う。わたしは洗濯物を畳む手を止めて、
「おかえり」
玄関先にまで顔を出した。しかし、その行為が累にとってあまり意味がないことをわたしは知っている。
「じゃあ、また行って来るね」
ランドセルと野球道具を入れ替えた累は、すぐさま家を飛び出していった。
累の背中だけを見つめながら、「気を付けてね」と言って見送る。
小学五年生の累が今最もハマっているものは、野球だ。
奇しくも、おとうさんと同じものにハマっている。
累はだいたい放課後になると、周りの友達と野球をする。そして、放課後だけに飽き足らず、土日の両日にも以前おとうさんが監督を務めていた地域の野球チームで野球をする。
わたしは興味がなくて良く分からないが、小学五年生なのに四番でピッチャーが出来るというだけで、その実力は折り紙つきだろう。
元々おとうさんが監督をしていた、という忖度を抜きにしても、累の能力は純粋に高いらしい。
元プロ野球選手というおとうさんの血を、累は受け継いでしまったのかもしれない。
加えて、累は努力が出来る人間だ。好きな野球が上手くなるための努力を、累は惜しみなく注いでいる。わたしも傑もスポーツがあまり得意ではないから、だいたい累は一人で素振りをし、一人で壁を的にしながらキャッチボールをしている。
もちろん、勉強にだって手を抜かない。小学校の先生達の通信簿の評価は、本当にわたし達の子供かなと疑ってしまうほどに高い。
努力を重ねる累を見て、わたしは――。
「ねぇ。傑からも累に野球なんて止めるように言ってあげてよ」
「え? なんで?」
土曜日の昼下がり、休みを言葉通り休息に当てる傑は、リビングのソファにうつ伏せになりながら動画サイトを徘徊している。ちなみに何の動画を見ているかは、夫とはいえ分かっていない。わたしも一人の時によく動画を見ているけれど、わざわざ傑に話すことはしなかった。
「いいじゃん。エースで四番だっけ。少年野球とはいえ、チームでそんな目立つ存在になれるなんて、我が子供ながらすげーじゃん。しかも、六年を抑えて、だろ。絶対すげー才能持ってるって。才能のままにやらせておけばいいんじゃないか?」
そう語る傑は、スマホから目を離さない。
出会った当初の傑の印象は、好青年そのものだった。人当たりの良い笑顔に、そばにいるだけで和む空気。傑がそばにいるだけで何とかなりそうで、そういう傑が好きだった。
けれど、結婚して分かった。
傑は好青年という訳ではなく、ただ波風を立てることを良しとしない性格なだけだった。人に嫌われたくないから、人に合わせて、調子の良い言葉を言う。よくよく注視してみれば、傑が自分の意見を言うことはほとんどない。自分の言動に責任を負いたくないから、無責任なことばかりだ。
もちろんわたしも似たような性格をしているから、それで良かった。
夫婦間の問題は、無難な方向に逃げることでなぁなぁに済ませることが多かった。
だけど、最近になって小さく頼りない背中を見る度、傑にはシャキッとして欲しいと思うことが多くなっている。――自分のことは棚に上げて。
「無責任なこと言わないで。傑、ちゃんと分かってるの?」
わたしはここであからさまに溜め息を吐いた。現実に背を向けて、怠惰に時間を過ごす夫と、わたしにしっかりと響くように。
「累は女の子よ? 野球にいつまでも時間を割いたって無駄でしょ」
<――③へ続く>
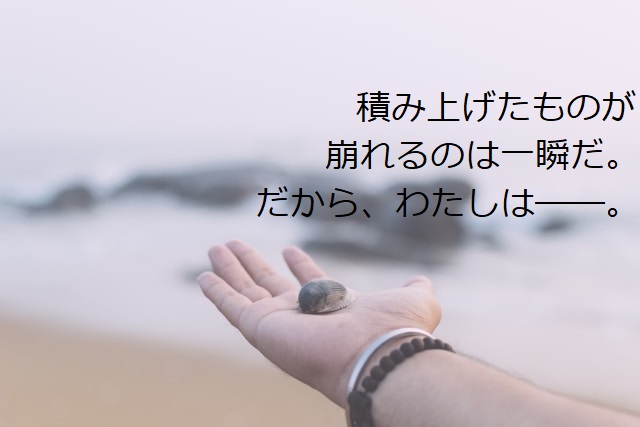



コメント