***
「はぁ、ほんっと激務」
先生の仕事というのは、担任を受け持って児童の面倒を見ながら、黒板の前に立っているだけではない。
全教科分の授業の資料づくり、テストの作成と採点、校内の掃除、児童の相談、家庭訪問、遠足や修学旅行などの行事の手配などなど――、定時外の仕事はもちろん家に持ち帰らなければ仕事をこなせない人もいる。
今もそうだ。
窓の外もすっかり昏くなっている会議室に籠って、本来の業務とは別の重たい業務に取り掛かりながら、私は机に全体重を委ねて一人文句を言った。
「望実センセー。文句はいいので、クリスマス向けの良い企画を考えてくださーい」
「魁里センセー、疲れすぎて頭が働きませーん」
会議室のホワイトボードの前に立って頭を悩ませているのは、相田魁里。
この小学校で働く同僚の中で一番話をするのは、間違いなく魁里だ。五年二組の担任をしていることに加え、同い年であることが大きい。児童の前ではちゃんと敬語でやり取りをしているが、こうして魁里と二人きりになると、私達は砕けた口調で話し合う。けれど、その口調さえも、あまりの疲労によって、更になおざりになっていた。
私たちは今、クリスマスに行なうイベントの企画と運営を任されている。
私たちが赴任している小学校では、季節のイベントごとに行事を企画している。たとえば今は、一か月経たずに迎えるクリスマスに向けて、学校全体を巻き込んだ行事をすることになっていた。
今回のイベントの統括に選ばれたのが、五年生の担任である私と魁里だった。統括に選ばれてしまったら、企画から運営、当日の司会まで、全ての責任を負うことになる。加えて、先生として求められる仕事も普通にこなさなければならないため家に仕事を持ち帰ることが多い。
残業代はみなしで固定になっているため、こんなに仕事をこなしても、給料は変わらない。お金を目的にして働いているわけではないはずなのに、少しだけ損をした気分になるのは何でだろう。
だから、イベントの統括は、ここの小学校で働く同僚の間では外れとされていた。
「企画、ねー。無難に体育館を使って、クリスマスソング歌えばいいんじゃない?」
日々の業務に忙殺されている私は、頬杖をつきながら、それっぽい企画を口にした。
こういうのは無駄に時間を掛けてアイディアを練っても、無駄になることが多い。だから、堅実で安パイな企画を考えて、実行することが一番いい。
しかし、私の思惑とは別に、「……いや」と魁里はホワイトボードと睨めっこをしながら言った。
「俺は今回のイベントは、ちゃんとやりたいと思ってる。もちろん望実が今言ったことも踏まえながら、もっと子供たちに寄り添った企画を考えてあげたいんだ。それこそ子供たちの想い出に、しっかりと残るものがいい」
そう言った魁里は、『プレゼント交換、豪華ランチ、ゲーム、キャンドルサービス、クリスマスソング』と思いつくことをホワイトボードに書いていく。
白い空間に、どんどんと黒が塗りつぶされていくのを間近で見て、私は辟易した。
魁里はよく理想を語る。「教育界を変えて、子供たちが安心して成長する現場を作り上げたい」――、そういう明確な目的を持って、魁里は教員資格を取ったそうだ。だから、普段の教員生活でも、こういった行事ごとでも、魁里は妥協しない。
確かに魁里が今書いた項目を実現出来たら、素敵だろう。全学年の子供たちの喜ぶ場面が、ありありと思い浮かぶ。
けれど――、
「ダメ」
私はハッキリと断わった。
魁里の思い描くクリスマス会をするためには、規模も費用も時間も、何もかもが足りない。
その変えられない事実を、私は理詰めで魁里に説明した。私の言うことを、ひとしきり頷きながら聞いていた魁里だったが、私の話が終わったところで、
「でもさ、それって、望実の希望だろ。望実が楽したいから、言ってるだけじゃん。確かに負担が増えるかもしれないけれど、俺たちが少し頑張れば何とかなるよ」
「楽とかじゃない。現実的に無理だって言ってるの。だから、最初に無難な案も出したじゃん」
「せっかくのイベントなのに、クリスマスソングだけって……。こんなんで子供がワクワクすると思ってんのかよ」
年が近いからこそ、私と魁里は自分が思ってることを赤裸々に言ってしまう。
出来る限り手数を少なくして堅実に物事を進めたい現実主義者な私と、苦労をしてでも出来る限り最高なものを作りたい理想主義者魁里は、あまりにも正反対だった。
私も魁里も、自分の意志を曲げるつもりはない。このまま話を進めても、平行線を辿っていくだけだ。
「あのさ」
溜め息交じりに魁里が口を開くと、
「望実って、我が儘言ったことある?」
突然放たれた魁里の質問の意図が分からなくて、「は?」と間の抜けた声が漏れ、すぐ
に「どういう意味?」と強い口調で問いかけた。魁里は左手で頭を掻くと、
「望実はいつも真面目で堅苦しいこと言わないからさ、本当に自分のやりたいことを言ったことあるのかなって思っただけ。なんていうか、いかにも箱庭育ちのお嬢様って感じ」
「――っ」
魁里の意見に反しようとした時、ちょうどチャイムが鳴り響いた。この小学校では、仕事に集中するがあまり教員が時間を忘れないように、一度十九時にチャイムが鳴るようになっている。チャイムの音にハッとした魁里は、自身を落ち着かせるように深く息を吐くと、
「ごめん、今日は終わりにしよう。お互いに考えて、週末に意見を出すってことでいいよな?」
理想論ばかり語る魁里なのに、魁里の口から出て来たのは、現実的な意見だった。
何も言わない私を見て、無言の肯定と受け取ったのか、魁里は会議室から出て行った。
魁里がいなくなって誰もいなくなった会議室で、
「――あるよ」
私は声を振り絞った。
我が儘を言ったことなんて、たくさんだ。昔の私は、自分のことをこの世界のお姫様のように思っていて、そのような振る舞いをして生きて来た。
それで迷惑をたくさん掛けて、それでその分痛い目に合ってるんだよ。
だから、もう一人でも現実を生きられるように、独りよがりな甘えた考えは封印するようになったんだ。
なのに、まさかあんな風に魁里から言われるとは思いもしなかった。
二時間近く籠って話し合ったというのに、ホワイトボードには決定的なアイディアが一つも浮かび上がっていなかった。現実的とは到底思えないアイディアたちを、私は一人で消していく。
<――③へ続く>
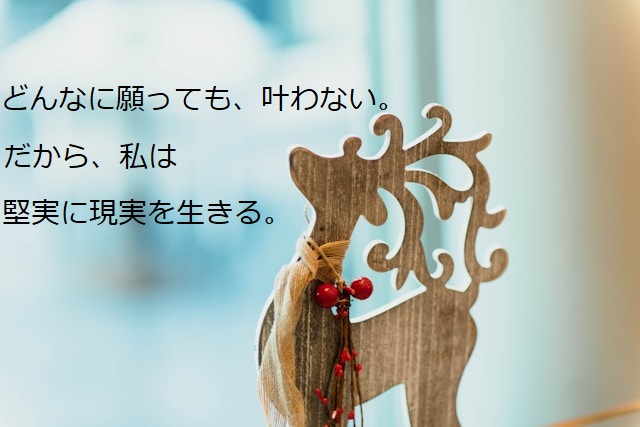



コメント