***
「飼育小屋で何かあったの?」
切羽詰まった杏奈に手を引かれてやって来た飼育小屋。
小学生にとっては少し大きくて、でも大人にとっては少し小さい籠の中には、兎が四羽いる。この小学校で飼育している動物はこの兎たちだけで、そのお世話は基本的には五年生と六年生に任されている。多くの児童に生命に触れてほしいという狙いのもと、週に二回ほどのペースでクラスの代表者一人が面倒を見るようになっていた。そういえば、今週のお世話をする担当者は、杏奈だった。
私の質問に言葉を返すことなく、行なうが早しと言ったように、担当者に委ねられている鍵を使って、杏奈は小屋の中に足を踏み入れていく。私も杏奈の後に続いて、飼育小屋の中に入った。自分たちよりも何十倍も体が大きい私たちを見て、兎たちはぴょんぴょんと距離を取っていく。
その一方で、唯一微動だにしない兎が一羽いた。
「あのね、この子、元気がないんだ。私が入っても動かないし、ご飯も食べてくれない……」
「ああ、ウサミね」
小学校の間で『ウサミ』という単純な名前を付けられたこの兎は、他の兎と少しだけ変わっている。
「ねぇ、杏奈ちゃん。ちょっとだけ後ろを向いてくれる?」
「え? うん」
不思議に思いながらも、杏奈は従ってくれた。その隙に私はウサミの前にそっと餌を置く。
「杏奈ちゃん、ウサミの方見て。出来るだけ、そーっとね」
私の言う通りに杏奈がゆっくりと振り返ると、
「わぁ、すごい!」
口元を抑えつつも、抑えきれない興奮を持って言った。
あれだけ微動だにしなかったウサミが、餌を食べているのだから当然の反応だろう。
「望実先生、望実先生っ! ねぇ、どんな魔法を使ったの?」
魔法って。子供らしい言葉選びに、私は心の中でくすりと笑んだ。
ウサミがご飯を食べるようになったことに、魔法も何もない。ただ単純に、ウサミは人の視線が苦手なだけだ。人から注目を集めていると思うと、ご飯を食べることはおろか、身動き一つ取れなくなってしまう。自然界に放たれたら危ぶまれるほど、繊細な心の持ち主なのだ。
だから私がしたことは、そっと餌を置いたら視線を反らすことだった。
全くもって大したことはしていないけど、褒められると嬉しくなってしまう。
「へへっ、内緒」
溢れる笑みを何とか抑えながら、少しだけ悪戯を仕掛けるように人差し指を唇に当てた。
「ずっといると兎たちも落ち着かないから、いったん出ようか」
私の言葉に、杏奈が「うん」と可愛らしく頷いた。静かに籠の中を出ると、私たちはもう一度籠を見た。四羽とも元気そうに動いている。
「ウサミも他の子も元気でよかった! ありがとう、望実先生」
「ううん、それは私の台詞だよ。声を掛けてくれてありがとね」
それから私たちは兎の可愛らしさについての話をしながら、グラウンドを横切って、校門を目指した。飼育小屋から校門までの距離は、いつもならあっという間に着くのに、今日は普段の倍近くの時間が掛かった。
「望実先生とたくさんお話出来て、とっても楽しかった!」
「先生も楽しかったよ。杏奈ちゃん、気をつけて帰ってね」
私は手を振った。「うん!」と元気よく言った杏奈だったが、何故か足は前に進んでいこうとしない。どうしたんだろう、と杏奈の動向を探っていると、
「ねぇ、望実先生」
上目遣いに、杏奈が私の名前を呼んだ。
「どうしたの?」
「私、毎年クリスマス会が楽しみなの! 望実先生が考えてくれるなら、きっと今年はもっと絶対楽しいよね!」
杏奈が大きく腕を使いながら、満面の笑みで言う。
目の前にいる子の全てが、あまりにも愛くるしくて。
「うん、杏奈ちゃんも皆も楽しくなるようなクリスマス会にするから任せてね」
私は杏奈の頭を優しく撫でた。「えへへ、うれしい」と、そのまま溶けてしまいそうなほど目を細めながら堪能していた。
そして、ひとしきり堪能し終えると、「約束だからね、望実先生!」と小指を突き出して帰路に着いた。
小さい背中が、更に小さくなっていくのを、私は手を振って見送る。すると、まるで私がちゃんといるのかどうか確認するかのように、杏奈は振り返り、体全部を使って大きく手を振る。私も杏奈に見習って、更に大きく手を振る。
そんなやり取りが、杏奈の姿が完全に見えなくなるまで続いた。ゆっくりと手を下ろすと、十二月の冷たい風が私の体を撫ぜた。
けれど、不思議と寒くはなかった。
今も私の手のひらには、すっぽりと覆えてしまえた小さくて柔らかい頭の感触が残っている。その温もりが、手のひらから全身に伝わって、心を満たしていく。
普段生活していては味わえない感動だ。
「……そっか」
きゅっと拳を握ると、私は校門から校舎へ向かって、走り出した。
私が先生になりたかった理由。それは、ただ真面目で堅実さを求められるから、という理由だけではなかった。
高校生の私は、現実を知って、夢や理想が崩れ落ちてしまった。自分が信じ、支えてくれていたものがなくなるというのは、思ったよりも辛いことだ。心にぽっかりと穴が空いてしまった感覚に襲われていた時、唯一私に寄り添ってくれたのが、当時の担任である杉田貴理子先生だった。
――「望実さん、困ってることはない?」
私と顔を合わせるや、いつもキリコ先生は声を掛けてくれた。自己中心的で先生の発言を無視するような生徒であろうと、悩みを抱えて暗い顔を浮かべるような生徒であろうと、変わらずに。
小学校の教員と高校の教員だから、正確には立場が異なるけれど、今の私なら先生がどれだけ忙しかったのか少しだけ分かる。なのに、当時の先生は忙しさを表に出すことなく、いつも余裕を心に保ちながら、優しく振る舞ってくれた。
そこで私は気付いてしまった。
私がどれほど周りの人に支えてもらいながら生きて来たのか。そして、いつも関心を持って見てくれている人がいるということが、どれほど大きいのか。
煩わしいな、と最初は思っていた。会う度に声を掛けられること、課題はちゃんと自分の力でやるように指示されること、生活態度を改めるようにさせること――間違っていることは間違っていると指摘する正論すべてが、嫌だった。
けれど、私の自分本位な態度に周りが離れていく中で、先生だけは変わらない態度で接してくれて、私という個人を見続けてくれていた。
当時の私がもし教師という立場に立ったなら、自分の思惑に反するような子は、すぐに切り捨ててしまうだろう。
けれど、キリコ先生は違った。
崩れ落ちていく私の理想を、キリコ先生が繋ぎ止めてくれた。
そのことに気付いた私は、キリコ先生を尊敬するようになり、次第に先生という職業に憧れを抱くようになった。
――「私、先生になりたいです」
進路決断をせがまれた時、私はキリコ先生に告げた。その時のキリコ先生の反応は忘れられない。
キリコ先生は、一瞬目を大きく見開かせた後、まるで自分のことのように大きく喜んでくれた。
「なんで忘れてたんだろう」
胸の奥の奥に霞んでしまっていた記憶に、私は呆れ混じりに疑問符を上げる。
けれど、その答えは明確に口にせずとも、自分自身が一番分かっていた。
現実に忙殺されてしまって、私はまたしても理想をなくしてしまっていた。絶対に忘れてはならない始まりの灯を、なくしてしまったのだ。
高校を卒業して大学生になって、本格的に取り組み始めようとすると、周りとは熱が違うことに気が付いた。過去の経験則を踏まえて、私は誰にも角が立たないような無難で堅実な行動をするようになってしまった。自分でも原型が分からなくなるほどに、私が抱いていた熱は、周りの風によって吹かれて消えた。
自分の理想通りに動ける魁里に、羨望と嫉妬の感情を抱きながらも、まだ自分の殻を破ることが出来なかった。
しかし、今、杏奈によって、私の熱は再燃した。
その熱に突き動かされて、校舎の中に入った私は、学校の廊下を駆け足で突き進み、職員室に向かうための階段を全力で駆けあがっていく。
私が本当になりたかった先生は、いつも変わることなく、子供たちに寄り添ってあげられる先生だ。
そのために今の私に出来ること。
それは――、
「魁里先生!」
自分の机で書類と向き合っていた魁里に私は声を掛けた。職員室に響き渡るくらいの声量になってしまい、職員室にいた先生たちから注目が集まってしまった。
けれど、今の私には関係ない。
「クリスマス会の話、しましょう。子供たち皆が笑顔になれる、最高のクリスマス会を作るために」
期限よりも早い言葉に、「まだ木曜……」と魁里は言葉を漏らした。
魁里の言いたいことは分かる。今週の初めに会議をして、何も浮かばないどころか空気を壊しかけたのだ。せっかく魁里が気を使って、週末まで時間をくれたというのに、わざわざ私は一日早めている。まるで自分の首を自分で絞めているかのようだ。
けれど、明日なんて待てなかった。このまま熱に従うことなく家に帰って、ただ明日を迎えてしまえば、きっとこの熱は冷めて消える。
この熱をなかったことにしたくなかったから、私から動き出して、明日を迎えに行く。
何か言おうとした魁里だったが、ふっと微笑むと、
「よっしゃ、やるか!」
机の上に広がっていた仕事を放って、勢いよく立ち上がった。
<――⑤へ続く>
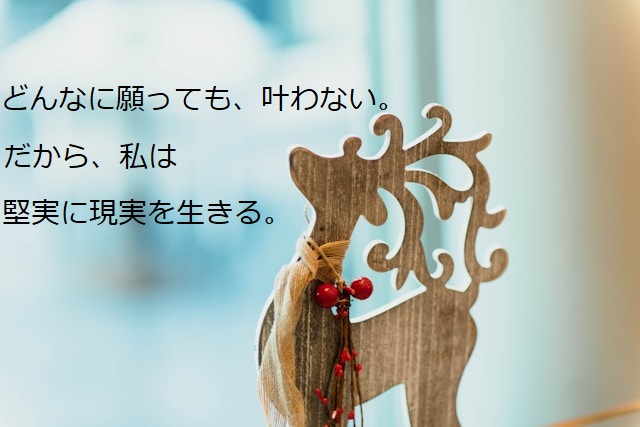



コメント