***
昔の私は、お姫様のように我が儘だった。
世界は自分のために回っていると本気で思っていたし、私がやろうとすることは何でも叶うんだって本気で思っていた。
だから、私は人の気持ちを慮ることが出来なかった。
その結果、
「望実、それは流石に自己中過ぎるよ」
今まで笑って受け入れてくれた友達が、私の行動を非難した。この時の私は、学校の課題を楽して丸写ししようとしていたのだ。その他にも、友達が食べてるお菓子を当たり前のように摘まんだり、私の買い物に付き合わせるだけつき合わせたり、先生や目上の人の言葉は軽く聞き流したり、気に食わないことがあればすぐに文句を言ったりなど、今思えば最低なほど酷い行動ばかりを振る舞っていた。
また、それだけではない。
「君のレベルだと、モデルとか芸能界なんて無理だね」
優しさによって持て囃されていただけの自分の容姿を勘違いして、芸能事務所に飛び込んだところ、思い切り突き放されてしまった。
ここで私の紛い物だった世界は、音を立てて崩れ落ちた。
気付けば、私の周りには、あまり人が寄らなくなっていた。
このように私の心を折るような出来事が立て続けに起こったため、この我が儘で自分本位な性格では生きていけないと悟って、現実的に生きることにした。
そして、高校生活を進む中で、職業としての『先生』を知り、先生を志すようになった。
先生に求められていることは、子供たちに真っ直ぐな道を示すことだ。
そのためには、子供たちの模範となるように、真面目で現実的に振る舞わなければならない。
夢から醒めて、現実主義者になった私にはピッタリな職業だと思った。
先生になるために、学ぶべきことを学んだ。授業について、子供の心理について、先生としてあるべき姿について、などなど。真面目な性格に方向転換した私は、黙々と知識を蓄えていった。
そして、念願叶えて先生になった私は、子供たちと接する時も真面目に接した。授業もちゃんとして、給食の時間や掃除の時間、また道徳の時間や学級活動なども、子供たちに嘘偽りなく、子供たちの益となるように振る舞った。
すべては子供の将来を守るため。
実際、子供たちもちゃんと受け止めてくれて、五年一組は問題の少ないクラスだと称されていた。
なのに――、
『望実って、我が儘言ったことある?』
魁里から言われた言葉が、ふとした拍子にフラッシュバックする。
この学校で五年の担任を勤めているのは、私と魁里だけだ。魁里の周りには、いつも子供たちが集まっているけれど、私の周りにはあまり集まらない。
必要最低限の時にしか頼ってもらえないのは、私に人気がないからだ。
真面目で堅苦しい先生より、気さくで楽しいことを語ってくれる先生の方が、子供たちにとっては良いのだ。
頭では分かっていた。なのに、その行動をすることが私には出来なかった。それは私の努力を足蹴にすることと同意だからだ。
そもそも大人になったら、我が儘なんて言えない。我が儘を言っていいのは、子供までだ。そのまま甘やかすように育ってしまったら、どこかの誰かさんみたいに、将来的に修正することは難しくなる。子供たちに不必要な苦労をして欲しくないから、私は真面目で、どこか無難な教育方針を選んだ。
けれど、とうとう魁里から直接指摘され、否定されてしまった。
私の個性――、必死に体質と思考を改革し続けてようやく手に入れた個性を拒絶されてしまったら、私はどうすればいいのだろう。
私のやり方は、先生という仕事に向いていないのか。
そもそもどうして、テンプレートに従うことしか出来なくなった私が、刻一刻と状況が転じる教育現場に足を踏み入れてしまったのだろう。
私の始まりの思いは――、
「望実先生、今いいですか」
魁里の声に、私はハッと顔を上げた。職員室の扉の近くにいるのは魁里。先日あれだけ言い合ったというのに、魁里は仕事だと割り切っているのか、いつも通りに振る舞っている
そして扉近くにいるのは、もう一人。
「杏奈ちゃん」
いつもの自信に満ち溢れた表情ではなくて、どこか申し訳なさそうな表情を浮かべている杏奈がいた。ランドセルのショルダーを命綱のように握り締めている。
取り組んでいた仕事と思考を放って、杏奈の元へ近付いた。
「何かあったの?」
「……」
柔らかな声音で訊ねても、杏奈は口を噤んだままだった。私も魁里もどうしていいか迷った。いつも元気溌溂な杏奈が、今何に悩んでいるのか分からないから、対処しようもなかった。
私は魁里に小さく目くばせした。私の意図をすぐさま察してくれた魁里は、小さく頷くと、職員室に入って自分の席へと戻っていった。
「あのね、望実先生、えっとね」
魁里がいなくなったことで、杏奈はようやく口を開くようになった。私にしか言えない悩みを抱えていることは分かった。けれど、まだ杏奈は言っていいのか迷いあぐねているようで、指をいじいじとしている。視線も合うことがない。
だから、私は膝を屈めて同じ視線になると、
「ねぇ、杏奈ちゃん。先生には遠慮しないで何でも話していいからね」
ニッコリと微笑んだ。ここまで視線が合わなかった杏奈の瞳は、少しだけ揺れていた。けれど、暫くの間、私と見つめ合っていると、だんだんとその瞳が真っ直ぐになっていく。
「ついてきて、望実先生!」
やがて、意を決したように私の手をギュッと掴むと一目散に走り始めた。杏奈の小さな手に引かれながら、杏奈の小さな背中を追いかけていく。目の前のことにひたむきで、人の事情なんて意図知れずなところは、子供らしかった。
そして、杏奈に連れて行かれた場所は、
「……飼育小屋?」
校庭の外れの方にある、私の身長と同じくらいの籠の前だった。
<――④へ続く>
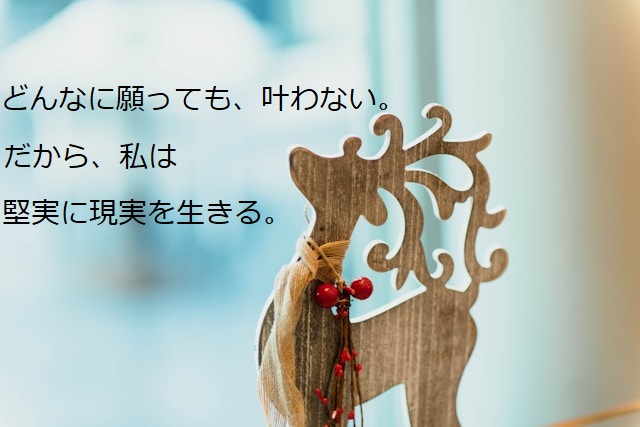



コメント