***
「良いイベントになったんじゃないか?」
祭りの後のような静寂に包まれる体育館で一人佇んでいると、後ろから声を掛けられた。
振り返り、「魁里」と彼の名前を呼んだ。
ジャージのポケットに手を入れている魁里は、先ほどまでクリスマス行事が行なわれていた体育館の中を、名残惜しそうに見つめていた。
今回の行事の統括を行なった私と魁里は、通常業務に加えて、イベントの企画から運営まで全てに携わった。何度も何度も会議をし、その度に良いアイディアが浮かび上がっては、いかに実現できるかを考えた。予算も時間も限られている中で、どこまで出来るか考えることは一苦労だった。
正直あまりの忙しさに、文字通り目が回ってしまい、倒れ込んでしまいそうにもなった。
堅実に生活しようとする私には、考えられない仕事量だったと思う。
けれど、その結果――、
「うん、すごく良かった」
結果、子供たちは終始笑顔でいてくれた。
クリスマス行事は、プレゼント交換を行なったり、クリスマスにちなんだミニゲームを行なったり、キャンドルサービスを行なったり、クリスマスソングを歌った。
帰りの会で児童たちの前に立った時、興奮冷めやらぬように子供たちははしゃいでいて、「最っ高のクリスマスだった!」と言ってくれた。私に熱を与えてくれた杏奈も、体全体を用いながら、私に感想を伝えてくれた。
この小学校に赴任して数年は経っていたのに、こんなにも多くの子供たちの心を動かせたのは初めてだった。
「ありがとう、魁里」
礼を口にすると、まるで心当たりがないかのように魁里は小首を傾げた。
「魁里のおかげで、私は自分が自分の可能性を縛っていたことに気付いたよ。堅実にやったら、確かに失敗することはない。けど、それだと誰の心も動かせない。変わるためには、どこかで一歩踏み出して、行動することが必要なんだね。魁里のおかげで、今回身に染みて分かった」
「あぁ。それを言うんだったら、俺もだよ。俺の独りよがりなアイディアだけだったら、最後まで実現出来なかったと思う。だけど、望実が楽しそうなアイディアを考えてくれて、それを実現するまでに何をするべきかを考えてくれたから、今回のクリスマス会が出来たんだ」
魁里がいなかったら、私は無難で現実的な内容を考えて、誰の心も動かせないつまらないイベントを作っていた。
私がいなかったら、魁里は誰かの心を動かすような楽しい内容を考えられても、現実的にイベントを運営することは出来なかった。
正反対な私たち。だからこそ、互いに足りないものを補い合って、クリスマス会を成功へと導いた。
今回のクリスマス会を通して、私たちは子供たちに夢のような時間を与えられたはずだ。
「私さ、昔はお姫様気取りの我が儘な女だったんだ」
唐突で突拍子もない私の言葉だったけれど、魁里は何も言わずに先を促してくれる。
「高校生になるまで、私は本気でサンタクロースがいるって信じてたし、本気で私が望むことは実現するって思い込んでいたんだよ」
――無条件に願っていれば、叶えられる。
そんな夢のようなひと時は終わった。いや、最初からそんなのはなかったんだ。
私の我が儘に付き合ってくれて、私をお姫様気分にしてくれるために奮闘してくれた人が周りにいたから、現実になっていただけなのだ。
私はどれだけ周りの人に迷惑を掛けていたのだろう。
「現実がそんなに甘くないことに気が付いた私は、現実に向き合うことにした。私が願うことは何一つ叶えられないって言い聞かせて、周りに迷惑かけた分、一人で出来ることだけを無難にこなそうと日々を送るようになったんだ。でも、違うよね。私がするべきことは、逆だったんだ」
「……逆?」
「過去周りに迷惑を掛けた分、周りの助けになるべきなんだよ」
キリコ先生が変わらない態度で寄り添ってくれたことで、私は大きく道を踏み外さないで済んだ。
ただの生意気な子供が夢を見続けられたのは、絶対に周りの影響が大きい。
だから、今度は私が同じようにしてあげたい。
「私、もっとこの職業に向き合いたい。子供たちが自分の道を真っ直ぐ進めるように、支えてあげるような人になりたい」
大人の力を借りてこそ、夢を実現できる子供たちのために、たとえ忙しくて時間が足りないとしても勝手に限界を定めず、行動していく。
そうしてこそ、私はあの時のキリコ先生のようになることが出来るはずだ。
「いい目標だな」
「魁里も理想を持ってるんでしょ」
「ああ。子供たちだけじゃなくて、その両親や働く教師たちも巻き込んで、いつか教育界を変えたいと思ってるよ」
「ははっ、やっぱすごいね」
私は心からの賛辞を魁里に送った。魁里が抱く理想は、やはり私が想像した何十倍も大きい。
私たちの理想は、いつ実現出来るか分からないほど、果てしなく大きい。
抗えない現実を前にして、いつか潰されてしまい、理想を忘れてしまうかもしれない。
けれど、まだ信じられる。
信じて、行動すれば、必ず――。
「……ところで、さ」
魁里が言いにくそうに声を紡ぐ。
「望実はいつまで帽子を被ってるんだ?」
今回のイベントで司会進行をするために、私はトナカイの帽子、魁里はサンタの帽子を被っていた。後片付けまで終わっているため、魁里はサンタの帽子をとっくに外していた。
「えへへ、似合うでしょ、これ」
私は子供たちの夢を叶えるようなサンタクロースになることは出来ない。けれど、夢を叶えるために手助けするトナカイにはなれる。
私が目指す先生は、トナカイのように寄り添って、そっと、でも確かに、道を導いてあげられるような人だ。
<――終わり>
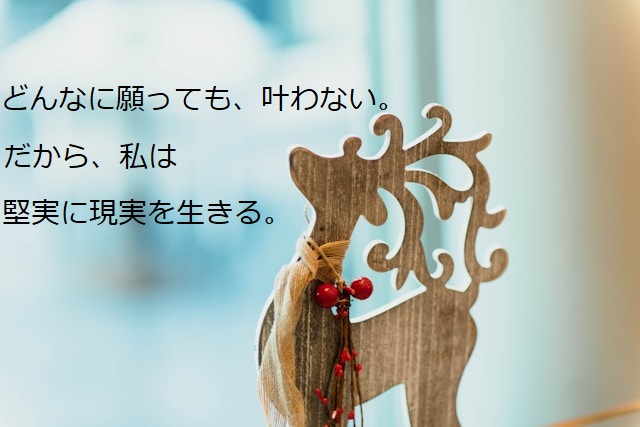



コメント