***
「基樹。お前、バンドの掛け持ちしてるのか?」
週二回のD・S・Eのバンド練習が終わるや、俺は意を決して質問をぶつけた。いつもポジティブで明るい晃英も、俺の声音から真剣さを感じ取ったのか、茶化すような言葉を挟まずにいる。
練習後のスタジオ内に、緊迫した空気が張り詰めていく。
そんな中、基樹の回答は、
「ああ、そうだが?」
何を当たり前のことを――、そう言いたげな雰囲気を漂わせていた。
一昨日のインディーズライブに友達の貞之と参加した時、『KiKi』という名前でステージの上に堂々と立つ基樹の姿を見た。しかも、基樹が助っ人していたのは、基樹に気付いたバンドだけではなかった。基樹は半分近くのバンドでベーシストとして立っていたのだ。
しかも、一つ一つのバンド演奏をおざなりにするのでもなく、全てのバンドで堂々と安定感のある演奏を奏でていた。
ステージに立つ基樹を見た時、俺の頭の中を「なんで」という言葉だけが蹂躙した。そして、その時に抱いた疑問を、
「なんでだよ? 俺たち、D・S・Eで本気でやっていくって話しただろ?」
一昨日に浮かんだ言葉のまま、基樹へと投げかける。
基樹と知り合ってD・S・Eを結成するようになってから、まだ一年弱。けれど、その間で、俺と基樹と晃英は絆を深めて来たつもりだった。
この三人でいつかプロの世界に駆け上がる。
そう信じて俺はD・S・Eに全力を注いで来たのに――、
「なのに、掛け持ちだなんて不誠実だって思わないのかよ」
「レベルが低いんだよ、榛也も晃英も」
溜め息を交えながら、基樹が言う。
「本気でプロ目指す? お前らの実力で何言ってるんだよ」
基樹が前髪を掻き上げた。普段隠れている双眸が露わになる。俺と晃英を見つめる基樹の目は、鋭く、冷めきっていた。
「自分の実力を分かってるのか? 俺は多くのバンドで経験を積んだからこそ、今の自分の実力の低さを悟った。正直、今の俺なんかじゃプロのベーシストになることは出来ない。だったら、もっとベースに触れる時間を増やして、もっと舞台に立つ経験をしなければいけない。だから、俺は自分の夢のために、多くのバンドを掛け持ちすることにした。その結論に至るのは必然だろ」
基樹がここまで長く一息に自分の思いを語るのは珍しかった。基樹の口は、動きを止めない。
「でも、お前らはどうだ。夢を成すとか言いながら、たった週二の練習で満足してやがる。特に榛也。このD・S・Eは、お前が始めたバンドだろ。なのに、お前は口ばかりで、本気でD・S・Eで成功しようという気概も行動も感じられない。俺の夢を、ただの夢見物語で終わらせようとするお前らの方が、よっぽど不誠実じゃないか?」
「……っ」
何も言い返すことが出来なかった。
基樹に言われた言葉の全ては、正論でしかなかったからだ。
だけど、それでも。
本気で夢を叶えたいと思っているのなら、ここで言い返すべきだったと思う。
「はぁ」
しかし、反論をする猶予すら与えることなく、今日何度耳にしたか分からない溜め息が再び漏れる。
いつの間にか基樹は前髪を下ろしていた。
「もういいや。お前らはこれがいいんだろ。なら好きにやれよ。俺も好きにやってくから」
基樹はベースを担ぐと、そのままスタジオの扉へと向かっていく。迷いのない足どりから、もう基樹の中で話が終わってしまったことを察することが出来る。
ここで黙って基樹を見送ったら、本当に全てが終わる気がした。
「おい、待てよ。好きにやれって、どういう意味だ?」
「言葉にしないと分からないか。俺は今日限りでこのバンドを辞める」
基樹は振り返ることなく、スタジオの扉に手を掛け、そのまま去っていった。
バンドを辞める?
基樹の言葉が頭の中でリフレインして、それ以上のことを考えることが出来なかった。
ちょっと待て。基樹がいなくなったら、D・S・Eはどうなる。俺はどこでドラムを叩けばいいんだよ。どうやって有名なドラマーになればいいんだ。
「あー、榛也」
茫然と立ち尽くす俺の耳に、遠慮がちに俺の名前を呼ぶ声が響く。ほぼほぼ惰性的に声の方へと顔を向ける。
どんな空気でも明るくしてしまう晃英からは考えられないほど真面目な表情だった。
それだけで、晃英が何を言おうとしているの予想出来た。
「悪い、俺もちょっと考えさせてもらっていいかな」
想像通りだった。
元々、晃英は俺が誘ったから、D・S・Eに参加してくれるようになっただけだ。俺や基樹のように絶対にプロになるという気概が、晃英にはない。
俺がどう返事をしたか分からない。気付けば、スタジオに残るのはただ俺独りになっていた。目の前には叩き慣れたドラムがある。
「――ぉッ!」
溜まりに溜まった感情を爆ぜさせるように、手にしていたスティックを思いのまま叩きつけた。
<――④へ続く>
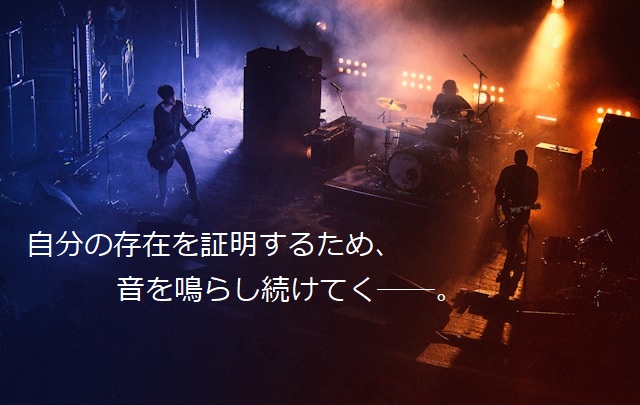



コメント