・糸と金①
***
昔から私は人とのコミュニケーションが下手だと自負している。
人と目を合わせることが苦手だし、最近の流行についていけないし、人と比べてやること成すこと全てが遅いし、そもそも何を話していいのか分からないくらい話すことが苦手だ。
だからこそ、私は誰とも関わらなくても楽しめる編み物を趣味にしている。
一人で完結する行動ばかりしていたから、学生時代に誰かと遊んだ経験なんて両手で事足りるくらいしかない。
それでも、こうして社会に出て仕事をこなすことが出来ているのは、『カリキュレーター』のおかげだと思う。
私は大学卒業と同時に、今の会社に新卒として勤めるようになった。私よりも目上の人にたくさん接しなければいけないことや慣れない仕事は、失敗してはいけないというプレッシャーを常に私に与えていた。編み物をする時間だけは何とか無心になることが出来たけれど、趣味に没頭する時間以外はストレスに苛まれて、気が狂いそうだった。
そんな時にたまたま出会ったのが、『カリキュレーター』だった。
事務所の力にも頼れない彼らは、デビューしてから半年が経つというのに、ビラ配りをして自身の存在をアピールしていた。しかし、多くの人はビラを受け取ることはせず、ビラを受け取っても立ち止まりもしないという状況だった。たまたまビラ配りをしている彼らの前を通った時、リーダーである升掛くんからビラを差し出された。咄嗟のことに何も考えずに受け取ると、「ありがとうございます!」と大きな声で言われた。しかも、それだけでなく、升掛くん以外のメンバーもビラ配りの手を止めて、私にお礼を言って来た。
こんなに多くの男性――いや、同性異性関わらず四人という少人数にすら囲まれた経験がなかった私は、「あ、あはは、はい、頑張ってください」と声を震わせながら、その場を離れた。
私がいなくなった後も、彼らはビラを渡せたことに大喜びしていて、また新たにビラ配りを始めた。それから、私のように立ち止まってビラを受け取るような人は現れなかったけれど、彼らは諦めることをしなかった。
いつかアイドルとして日の目を浴びられることを信じて、自分たちに出来る目の前のことを一つ一つ行なった。
その姿に感動した私は、『カリキュレーター』の動向を追うようになり、気付けばただのファンになってしまった。
仕事で嫌なことがあった時は『カリキュレーター』の歌を聞き、仕事終わりには無心で編み物をする。
そんなルーティンをこなす内に、いつしか私は社会人としての生活を送ることに苦を感じなくなり始めた。ストレスから逃げられる場所が大きかった、と今なら思う。
「まぁ、なんとか人としての生活ラインを保ってるだけで、季節のイベントとは相変わらず無関係だけど……」
会社の近くの公園で昼休憩を取りながら、私は小さく呟いた。
世間はもう十二月。あともう少しすればクリスマスになり、クリスマスが終われば年の瀬になってしまう。
町中を見渡しても、どことなく浮いた空気が漂っていることが感じられるようになって来た。それは、私が今いる公園も同じことが言えた。
季節のイベント事、特にクリスマスになると、恋人同士でいることを強いる風潮が強くなる。誰かと付き合ったこともない私は、いつも他人事のように達観していた。
「別に寂しくもないしね」
一人という寂しさを紛らわせてくれる趣味が、私にはある。
今も昼休憩の時間を使って、昨日の編み物の続きを行なっていた。
普段であれば、勤務時間中に編み物グッズを持ってくることはしないのだが、今日は特別だった。昨日の夜、仕事の疲れからか中途半端なところで寝落ちしてしまった私は、朝目覚めるや作りかけの編み物を見て、キリのいいところまで編みたい衝動に駆られてしまった。しかし、仕事もあって編み物に当てる時間を取れない私が選んだ策が、職場まで持っていくということだった。
いくら休憩中とはいえ、さすがに職場内で編み物をすることが出来ないから、こうして外で編み始めてみたが意外と楽しいものだ。
午前中もドタバタしていて自分の仕事の出来なさに悔しさを感じたりもしたが、休憩中に編み物をすることで、いい気分転換になっている。
外で編むということに今まで気付かなかったのが不思議なくらいだ。
これなら今までよりも速いペースで編み物を作ることが出来る。マフラーも手袋も、セーターだって完成させられるかもしれない。考えただけで楽しくなってしまう。
「あ」
そう妄想を膨らませたところ、編んでいた赤い毛玉が風によってベンチから落ちてしまった。
十二月の寒い時期に外で編むことはおろか、会社の近くの公園で編み物に取り組んだことなんて一度もなかったから、こういった小トラブルを失念していた。
毛玉が糸を伸ばしながら、ドンドンと転がっていく。まだ糸は全然消費していなかったから、このまま転がってしまえば、どこまでも転がってしまうだろう。
「やば」
急いで立ち上がって拾いに行こうすると、歩行者の足元にぶつかって、毛玉が止まった。男物の革靴を履いたその人は、赤い毛玉を拾ってくれた。
「すみません、ありがとうございます」
歩行者から受け取ろうと思って歩み寄った時、その人の顔が見えてしまって、私は足を止めてしまった。
「これ、細田の?」
私の名前を呼んだその人物は、私と同じ会社に勤めている同期の冴島銀河だった。
冴島くんは総務部とは隣の部署である営業部に所属していて、その甘いマスクと、堂々とした態度によって多くの売上を叩き出し、わが社の稼ぎ頭となっている。同じ会社で働く女性社員はみな、冴島くんのことを気にしているほどだ。
いつも色んな会社に渡り歩いて忙しくしている冴島くんが、どうして事務所の近くの公園を歩いているのだろう。
冴島くんは私の手に赤い毛玉を握らせると、
「何やってんの、細田」
「え、いや、その、こっちの台詞、です……」
冴島くんとは同期なのに、いつまでも敬語を抜くことが出来ないのは、私が冴島くんと比較してしまっているからだ。いや、冴島くんだけじゃない。他の同期や、よく出来る後輩に対しても、いつも天上の人として接してしまう。
「俺は経費の精算とかする必要があるから、昼休憩のタイミングで戻って来たんだよ」
頭を掻きながら、「まぁ、総務部の人はみんな昼でいなかったけどさ」と冴島くんは言う。
「へ、へー、そうなんですね」
こういう時、私は言うべき言葉がすっと出てこない。「うちの部署、みんな時間守ってますからね」とか他愛のない会話が浮かぶのは、いつも沈黙という気まずい空気が流れてからだ。
しかし、ここでいつもと違う雰囲気を感じ取った。冴島くん以外の人であれば、「じゃあ、またね」とこの場を切り抜けようとするのに、冴島くんはずっと立ったままだ。なのに、何かを言うでもなく、私を見据えている。いや、違う。正確には、私の背後を見ている。
――私の、奥……?
冴島くんの視線の先にあるものを理解した時、全身の血が一気に引いていくのが分かった。
赤い毛玉だけだったら、まだ言い訳のしようもあった。けれど、毛糸が伸びた先にあるのは、私の編みかけのマフラーだ。ひそやかな私の趣味がバレてしまう。
「細田、もしかして……」
「あ、あの、拾ってくれてありがとございました。午後からも頑張ってください」
私は冴島くんの言葉を遮るように頭を下げると、そのまま逃げるようにベンチに戻った。転がって伸びた糸は、適当に巻いて集めたから雁字搦めになっている。本当は丁寧に糸を集めたかった。でも、そんなことが些細に思ってしまうほど、冴島くんの前から離れることを優先させる。編み物セットをぐちゃぐちゃに鞄の中にしまうと、私は会社が入っているビルへと走る。
冴島くんが何か言いたそうにしていたけど、全力で気付かないフリをした。
――なんかお祖母ちゃんみたいな趣味だね。
小学校の頃、私の趣味を明らかにした時、同級生から引き攣った笑顔で言われた。大人になってからも、会社の同僚たちがハンドメイドの動画を見ながら、「絶対ブランドものの方がいいっしょ」と馬鹿にしていたのを耳にしたことがある。
編み物が趣味だって、私は知られてはいけなかった。
なのに、よりにもよって、会社の中でも影響力がある冴島くんに知られてしまった。
せっかく波風立たずに過ごせるようになった職場も、きっと荒れるに違いない。
会社のビルに入った私は、すぐに自席に戻ることはせず、トイレの中に駆け込んだ。
「どうしよ、どうしよ、どうしよ」
個室の扉に背中を預けて、私はまるで呪詛のように何度も何度も呟いた。
頭の中で先ほどの冴島くんの顔が浮かぶ度、心臓が痛いほどに逸る。
その一方で、今朝のニュース番組で引地くんの過去を暴露するシーンが思い浮かんでいた。
コーナー自体はいつも通りで、『カリキュレーター』が最近の流行りの商品を紹介していくものだった。しかし、その途中で話が盛り上がり、引地くんの過去を無理やり吐かせようとするコーナーが始まった。今思うと、なんでそんな流れになったのかは分からない。けれど、一つ言えることは、引地くんは今アイドルが出来ていることが不思議なほど過去にトラウマを抱いている人だ。以前、公式チャンネルで引地くんがそう言っていた。しかし、生放送なのにも関わらず、引地くんは過去を暴露することを求められてしまった。不穏な空気がスタジオに流れたのか、そのままCMに入ってしまい、出社の関係でその後の結果を知るすべがなくなってしまった。
引地くんはどうやってあの局面を切り抜けたのだろう。
私だったら、トラウマに苛まれて、抜け出そうと足掻けば足掻くほど、実体を伴なって私の傷を抉りに来るような感覚に陥ってしまうだろう。
これは私の悪い妄想だ。まだ現実には何も起こっていない。もしかしたら、冴島くんは何も気付いていないかもしれないし、気付いたとしても何も言わないかもしれない。そもそも、私なんかのことを話題に上げたとしても、退屈そのものだ。
頭では分かって、そう胸に言い聞かせているのに、どうしても心が理解を拒んでいる。
こんなにも心がマイナスに陥るのは、『カリキュレーター』に出会って以来初めてのことだ。
ここまで何とかプラスに保っていた心が、急速にマイナスに傾いていくのが、自分でも分かった。
昼休憩が終わるまで、あと五分。
マイナスに傾いた心は戻らない。でも、せめて仕事をこなせるくらいにマイナスの振れ幅を小さくさせたい。
昼休憩の終わりを告げるチャイムが鳴るまでの間、死刑宣告を受けたかのように顔を真っ青にさせていた。
<――③へ続く>
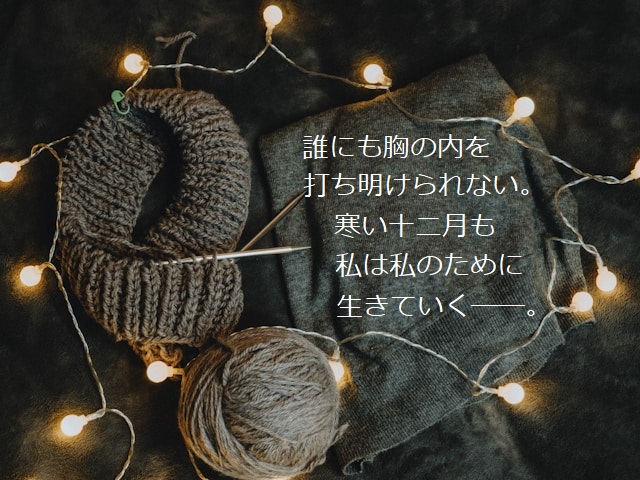


コメント