・糸と金①
・糸と金②
***
いつも仲が良いことで知られる『カリキュレーター』だが、メンバーである割崎くんが放った一言で、グループの空気は険悪なものへと変わった。
割崎くんはグループの中でも、ちょっと違うタイプの子だ。
みんなをまとめるリーダーの升掛くん、元気溌剌な姿が周りを明るくさせる鎌足くん、グループ一のクールキャラだけど実は誰よりも繊細な引地くん、そして、自己中心的な態度でグループをかき乱す割崎くん。
自分が思ったことをすぐに言葉にしてしまう割崎くんは、『カリキュレーター』の楽曲の中でも気に入らないものがあると、すぐに不満や文句を、SNSなどにアップする。その文句とは裏腹に、ダンスの振り付けなどはしっかりと取り組むから、メンバーもファンも割崎くんのパフォーマンスとして受け止めている。
しかし、この前の朝のニュースのコーナーで言った一言は、割崎くんのキャラを加味しても炎上してしまった。
内容は、こうだ。
――「カリキュレーターがもっと有名に必要なこと? そんなの簡単すよ、俺が四人いればいい。そうすりゃ、パフォーマンス面でも、歌唱面でも、もっともっと上に昇ることが出来る」。
この発言が、一般人の間でも反感の種となり、割崎くんのことを知っているファンの間ですらも意見が二分化した。『カリキュレーター』の残りの三人は、またいつものことかと達観したように割崎くんの問題に触れないようにした。
しかし、それでも『カリキュレーター』の空気が固くなっていることは、ファンからしたら誤魔化すことは出来ない。
売れるかどうかが掛かった大事なこの時期に、割崎くんのたった一言で、グループの勢いは止まりかけている。
周りから頭一つ飛び出してしまった釘に待ち構えるのは、打たれることだけ。
割崎くんの一件は、改めてそう私に教えてくれる。
「今年もお疲れ様でした!」
そんなことを考えながら、人の声と熱気で賑わう居酒屋で行なわれている忘年会に参加していた。
会社の全部署が一堂に会する機会は、年に数回しかないのだけど、この忘年会もその数少ない場だった。
しかし、私に話す同僚なんていない。周りにいる同僚たちの話に合わせて、うんうんと頷きながら、温かいお茶をちびちびと飲むだけだ。
隣のテーブルで談笑している冴島くんに、ちらりと目を向ける。
そこにいるのは、冴島くんと、私とほとんど同年代の女性社員たちだ。老若男女問わずに人気がある冴島くんは、彼女たちの中心になって、場を盛り上げていた。その影響力は、冴島くんのテーブルだけでなく、右隣である私のテーブルと左隣のテーブルまで巻き込むほどだった。そして、ひとしきり話をすると、また別のテーブルに顔を出しにいく。こういう小さな気遣いが出来るからこそ、冴島くんは多くの人から好かれ、また営業でも好成績を出すことが出来るのだろう。
社交性がゼロの私は、こういう時、人から話しかけられるのを待つ傾向がある。そして、私みたいな暗くて何を考えているか分からない奴に話しかける人はいない。だから、いつも私は輪に馴染むことが出来ずにいる。
お茶で何とか気持ちを紛らわせながら、周りに目を向ける。
上司や同期、更には後輩たちも楽しそうにしていた。そして、同期たちの服装を見ると、
みんなブランド物の服やアクセサリーや服を身に着けていた。一方、私は一昔前に編んだセーターを着ている。本物の華やかさを目の当たりにすると、手作り感満載の安っぽい服を着る私は偽物であるということを突きつけられてしまう。
私はみんなと違う。みんなが普通に出来ることを、私には行なうことが出来ない。
それでもなんとか、編み物だけに縋っていた昔の私と比べて、『カリキュレーター』と出会ったことで、私は少しだけ世間を渡り歩けるような気がしていた。
でも、違う。私自身の行動は何も変わっていない。頑張っている『カリキュレーター』を見て、私も頑張っている気になっただけだ。
本当に変わるためには、周りによって変化した気分を味わうのではなく、自分自身が動かなければならないのだ。
今まで何とかプラスに保っていた私の心が、割かれていく。何度も何度も、もう割れるところなんてないくらいに粉々に割り砕いてしまったら、私に何が残るのだろう。
ただただ消えてしまいたかった。
「……」
ずっと俯かせていた顔を上げた時、先ほどまで冴島くんがいたテーブルに座っている同期の権藤さんと目が合った。権藤さんは私と同じ総務部に所属していて、私とは違って、ギャルみたいな飾らない明るさによって周りから可愛がられている。同期で同じ部署で働いているのに、私と権藤さんはあまり接点がない。
なのに、赤らめた顔をした権藤さんは、確かに私を見て笑った。
私はあの笑い方を昔見たことがある。
「ただいま」
冴島くんが私の隣のテーブルに戻って来た。権藤さんの方に視線を向けていたからか、自然と冴島くんと目が合った。
普段であれば、何も反応がなかったはずだ。しかし、冴島くんは私を見るや目を見開かせ、友好的な笑みを浮かべた。
そして、そのまま下ろしたばかりの腰を持ち上げた――
「冴島もそう思うでしょ」
――ところで、権藤さんから声を掛けられた。
「なんの話?」
心なしか、冴島くんの声の温度が、いつもよりも低く感じられた。
けれど、この飲み会の場で気が付いているのは、酒を口にしていない私だけだろう。
「細田さんの服の話。いかにも手作り感満載の服なんてダサいでしょ」
権藤さんの話は、私の耳に聞こえていなかった。笑われたと思っていたのは、私の手作りのセーターを馬鹿にしていたからだったのか。
自分で編んだセーターが、流行りとは違うってことは分かっている。馬鹿にされていることも覚悟していた。けれど、いざハッキリと口にされてしまうと、ショックを受けてしまうのはなんでだろう。
「ああ、確かにダサいな」
冴島くんは躊躇いもなく言った。
別に冴島くんが何かしらのフォローをしてくれるだろうなんて、思ってもいなかった。冴島くんと私は、住む世界が全然違う。もしここで冴島くんが彼女たちに反することを言えば、ここの空気が冷めて、明日から冴島くんが仕事をやりにくくなってしまうだろう。
だから、仕方ない。
私の心なんて、他の人には関係がないのだ。もう割れるところなんてないくらい心が粉々になってしまったとしても、奥へ奥へと追いやれば、その場しのぎだけは出来る。
そして、あとで家になったら、独りで処理すればいい。
「あはは、冴島ならそう言うと思った。やっぱ細田さんのセンスってダサいよね」
「ああ、違う違う。俺が言ったダサいっていうのは、人のことを笑うお前らのこと」
そう言い切った冴島くんの一言で、せっかく盛り上がっていた場の空気が、一瞬にして冷めきってしまった。
<――④へ続く>
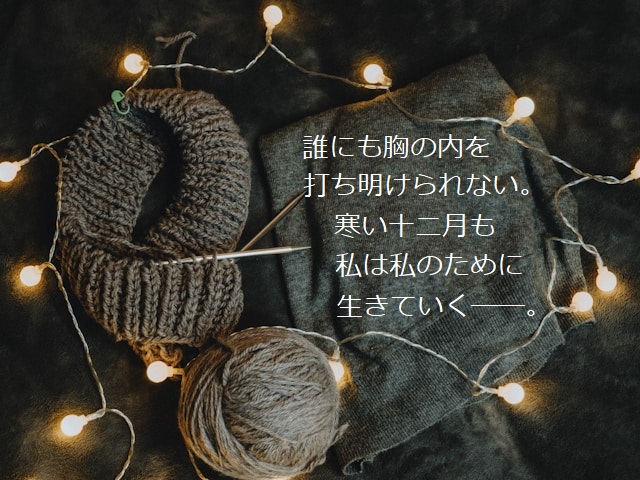


コメント