・糸と金①
・糸と金②
・糸と金③
***
忘年会という楽しい空気が蔓延するはずの場所に、一気に冷たい空気が押し寄せて来た。
その発信源は、社内でも人気のある営業部の冴島くんと、ギャルのような明るさで総務部の中でも人望が厚い権藤さんだ。
みんな二人が一触即発の空気を放つ二人を、皆がハラハラとしながら見守っている。
しかし、誰が予想できるだろうか。この空気の大元の原因を作ったのが、会社の中で目立つことのない私にあるなんて。
「は? なんて言ったの?」
「ダサいのはお前らだ、って言ったんだよ」
睨みを利かせる権藤さんに対して、冴島くんは全く動じることなく自分の意見を貫く。色んな会社の人たちを相手に営業しているからか、冴島くんの心臓には毛が生えている。
「お前らに細田の何が分かるの?」
「分かるでしょ、ずっと同じ場所で働いてるんだから。仕事は遅くてミスだらけ、そのくせ自分から話しかけることもなく愛嬌もない、加えてファッションセンスも壊滅的。何考えているか分からない女、それが細田だよ」
確かに否定しようもないくらいその通りなんだけど、改めて権藤さんの口から聞かされる私の評価に、少しばかり心が折れそうになる。
しかし、冴島くんは権藤さんの言葉を聞いても、呆れるように息を吐いた。その態度に、「冴島だって、細田のこと知らないでしょ」と権藤さんが嚙みつく。
「少なくともお前らよりも知っていることは多いよ」
冴島くんと私は、同じタイミングで会社に入っただけの関係だ。一緒にご飯を食べたこともないし、何か趣味の話をしたわけでもない。もちろん仕事面でも違う部署に所属しているから、私の仕事ぶりなんて知っているはずがない。
なのに、冴島くんはこれから一体何を言おうとするのだろう。
「細田は忍耐のある奴だよ。これだけ周りから何と言われようとも、細田はずっと仕事を続けている。仕事が遅いのだって、一つ一つのことにしっかりと向き合おうとしている証拠だ。でも、何よりも俺が細田のことを凄いと思うところは、ハンドメイドっていう趣味を持っているからだよ」
「……はい?」
冴島くんの言葉に、私の頭は一瞬理解が追いつかなかった。今、なんて言った?
「細田が今着ているセーターは、自分で作ったものだ。それだけじゃない、細田は身の回りの物を自分で作っている。自分が好きでやっているとはいえ、ここまで出来ることは素直に褒められることだろ」
「あ、あの、なんで冴島くんは私の趣味のこと知ってるんですか? 誰にも言ったことないから知られてるはずもないし、この前の毛糸玉だってあれ一つで気付くはずが……」
聞き間違いではないことを悟った時、私は冴島くんに問いかけていた。周りの人も、「知ってた?」と互いに確認をし合っては、首を横に振り合っている。
「一目見れば、それが手作りかどうかなんて分かるだろ。それを細田はずっと着てるんだ。気付いてください、って言ってるようなもんだって」
「いや、それは……」
せっかく作ったのに使わないでいるのは勿体ないという理由だけで、誰かに気付いてもらいたいという理由では決してなかった。
「あぁ、だからいつもダサい服着てるんだな」
ここで暫く黙っていた権藤さんが声を出した。悪態を吐けるタイミングを逃すまい、としているのだろう。
「は、なんて言った? 権藤」
しかし、冴島くんの口からは、冷めきった声が飛び出した。
今まで耳にしたことのない声に、発言者の権藤さんだけでなく、ここにいる誰もが身を固くさせた。当事者の私をおいて、冴島くんの気持ちはヒートアップしていく。
「たった一本の糸から、ここまでの服を作るってどれだけ大変か想像してみろよ。自分でも実際にやって悪く言うなら、百歩譲って分かるよ。でも、お前さ何にもしてないだろ。そんな奴に何か言う権利なんてないよ」
包み隠さない冴島くんの本心をぶつけられ、権藤さんの眦に涙が浮かび上がった。けれど、その涙を流さないように、鋭い眼差しで冴島くんを睨み付ける。
このままじゃダメだ。
当事者である私が何か言わない限り、きっとこの場を丸く治めることは出来ないだろう。
「冴島くん、もういいです。その、ありがとう、ございました」
私の声が小さかったのか、冴島くんはまだ権藤さんに何かを言おうと口を開く。
「それにさ、権藤の普段の生活からしてさ、仕事に対しても適当じゃん。そんな奴は、絶対に何かを根気強く作ることなんて出来ないって。だからさ、権藤はもっと細田のこと見習った方がいいよ」
「そんなことない!」
気付けば、私は席から立ち上がって声を張り上げていた。
驚いたような権藤さんや周りの視線が、やけに痛く鋭く突き刺さる。唯一動揺していないのは冴島くんだけだ。
けれど、もう火蓋は切って落とされたのだ。後に引くことは出来ない。
「冴島くんは外回りで営業してるから分からないだけだよ! 権藤さんはいつも総務部を明るくしてくれたり、大変な仕事だとしても、文句言いながらでもちゃんとやってくれる人だよ。今の言い方は権藤さんに失礼だから、謝って!」
ここまで一息に大声で言うと、私は肩で息をした。少しだけ冷静になって周りを見る。権藤さんが目をぱちくりと開けながら、口を小さく開けていた。
冴島くんが権藤さんのことを悪く言うことを聞いて、つい頭に血が上ってしまった。でも、まさかここまで周りに目を向けられなくなるとは思いもしなかった。
しかし、突然大声を向けられた当の本人である冴島くんは全く気に留める素振りを見せていなかった。それどころか、笑みを濃く浮かべて、
「これが細田のすごさだよ」
場違いに褒められて、「へ?」と間の抜けた声を漏らしてしまった。
「自分を悪く言う相手に対しても、細田はちゃんと誠実に見てるんだ。こんな風に出来る奴、そうはいないだろ」
権藤さんも、その近くに座っている女性社員も、何も言えずに俯くだけだった。
「お前らさ、細田の優しさに甘えてばかりいるなよ」
そう言うと、冴島くんは外に出て行った。すると、忘年会とは思えないほど空気がしんと静まった。
その一方で、あんなにも割れんばかりに傷付いていた私の心は、不本意にも弾んでいた。まるでマイナスにマイナスを掛けたら、プラスになったかのようだ。
私は冴島くんの後を追いかけるため、この場を離れることにした。冷めて張り詰めていた飲み会の空気がふっと動いた気がしたが、私は気に留めることをしなかった。
お店の外に出ると、冴島くんの背中が見えた。
「ねぇ、冴島くん! 待って!」
遠くなる背中に呼びかける。すると、その背中は立ち止まって、私を振り返った。
何度も何度も冴島くんとは顔を合わせているはずなのに、この時初めて向き合ったような気がした。
私が隣まで追いつくと、冴島くんはゆっくりと歩き始めた。
駅まで方角は一緒だ。私も冴島くんの左隣に並んで一緒に歩く。
「さっきのはなんで……」
常に冷静だと思っていた冴島くんが、あんなにも自分の意見を――、しかも私なんかのことについて言うことが珍しくて、そう問いかけた。
「同志が貶されかけているのに、放っておくことなんて出来ないだろ」
当たり前のように言い放ったけど、私は理解が出来なかった。私と冴島くんが同志って、どういう意味だろう?
私が何も反応を示さなかったからだろう、冴島くんは左髪を耳にかけた。冴島くんの左耳には、金色のピアスがついている。
「これ、俺が作ったんだよ」
「え?」
「形は違えど、ハンドメイドを趣味に持つ人間として、俺は勝手に細田に仲間意識を抱いていたんだよ」
冴島くんは自分の趣味を包み隠さずに話してくれた。
――今朝のニュース番組のコーナーで、『カリキュレーター』のリーダーである升掛くんが出演していたシーンが思い浮かぶ。
メンバー間で仲直りしたので心配を掛けてしまったことへのお詫びと、年明け後に比較的大きな箱でライブをすると広告していた。
その時、升掛くんが言っていたことが、私の心に響いている。
「考え方や性格の違いのせいで、前に進んだり、後戻りしたりすることもありました。でも、足して引いて掛けて割った結果が、俺たちカリキュレーターなんです。起こりえる物事に、意味のないことなんてない。どんな逆境でも、俺達は楽しんで乗り越えますよ」
<――⑤へ続く>
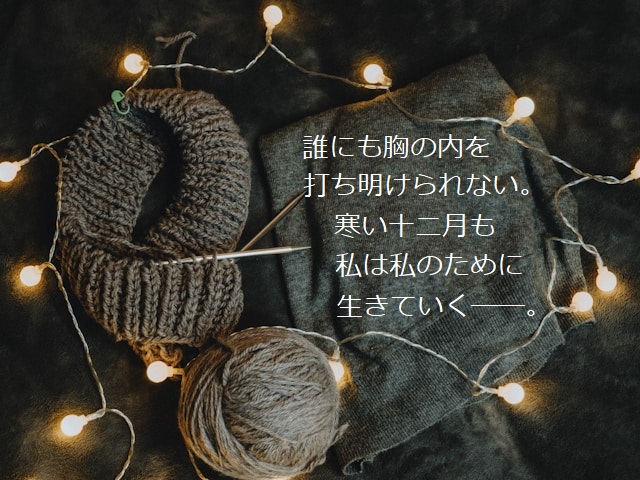


コメント