・糸と金①
・糸と金②
・糸と金③
・糸と金④
***
年内最後の仕事ということもあって、会社の計らいにより退勤時間が一時間ほど早まった。私と同じ境遇の人が世間一般でも多いのか、オフィスビルを出るや、いつもよりも多くの人が帰路に着こうとしていた。
一年という月日はあっという間だ。ずっと続くと思っていた苦痛も、いざ振り返ってみれば、手の届かないほど遠く彼方に追いやられていることもある。
あと数日もすれば、新しい年。きっと感傷に浸る間もなく、新しい年を迎え、いつの間にか終わりを告げるようになる。
でも、今はまだ来てもいない来年のことを考えるのは尚早だ。
「何しよっかな」
家に帰った後のことを考える。一週間ほどの休みをどうやって過ごそうか、今から楽しみだ。
このまま帰れば、今日は満員電車に巻き込まれずに帰れそうだ。
駅に向かって歩いていると、シャキッと背筋を伸ばしている背中を見つけた。
その背中に声を掛けるかどうか一瞬の間考えたが、私はすぐさま駆け出して、
「冴島くんも終わり?」
以前の私からは考えられない行動に出た。冴島くんは私のことを見ると、笑みを浮かべて「おう。今年も一年お疲れさま」と労いの言葉を掛けてくれた。冴島くんの声に、「うん、お疲れさま」と、まるで普通の同期のように声を掛ける。
まさか会社の中でも優れた成績を誇る冴島くんと、こうして話す日が来るようになるとは思わなかった。
ほんのちょっと前までは、冴島くんに対して感じていた距離は、共通の趣味を持っていたことによって解消された。
会社の忘年会があったあの日、冴島くんは私に自分の趣味を明かしてくれた。
冴島くんの趣味はハンドメイドでアクセサリーを作ることで、休みや時間がある時は、いつもアクセサリーを作っているらしい。アクセサリーを作ることの難しさや楽しさを聞いている内に、あまりにも共感できることが多くって、いつの間にか私も自分の話をしていた。
あれだけ自分の趣味を語ることを疎んでいたのに、いざ話してしまえば、今までの恐怖心は何だったのだろうと思うほどスムーズに言葉が出た。
でも、それは共通の趣味を持つ冴島くんが相手だったからだと思う。
冴島くんは自分の手で物を作ることが好きで、人へ話をするのが上手い以上に人の話を聞くのが上手い。
だからこそ、今までの堰を切るように、私の口は止まらなかったのだ。
「ねぇ、冴島くん」
私は鞄の中から赤いマフラーを取り出した。
「これ、この前言ってたやつ。私が作ったやつなんだけどね」
「おお、すごいな」
いつもの爽やかなスマイルを浮かべながら、冴島くんは私の手から赤いマフラーを受け取った。その柔らかな手つきは、作品の価値を分かっている人のそれだった。そして、「へー、丁寧に作ってるんだな」とマフラーをジッと見ながら褒めてくれた。
「これ作るの大変だったでしょ」
そして、私の苦労に寄り添うような言葉を投げかけてくれる。
なるほど、これは周りから人気が出るはずだ。
そんな相手を前に、私はこれから今までの自分ではあり得なかったことをしなければいけないのだ。
「えっとね、そうなんだ。実はね」
心臓が高鳴って朦朧とする頭を何とか動かして、声を出す。
「これ、もしよかったら、冴島くんに貰って欲しいな」
ただ静かに冴島くんが私のことを見る。「え、えっとね、この前の忘年会の時の、お礼? みたいなものだから。それに、私は編み物いっぱい持っているから、その、ね」と言い訳のような言葉が、私の口からどっと漏れ出していく。
本当だったら、もっとスマートに渡す予定だった。でも、まだ人に慣れておらず、プレゼントを渡した経験もほとんどない私は、渡せただけでも大きな一歩だろう。
しかし、冴島くんは、
「ありがとう、大切にするわ」
と言って、その場でマフラーを首に巻いてくれた。
マフラーを編み出した最初の目的は、首元の寒さを凌げればいいな、という自分のためのものだった。いや、目的なんてものはなくて、いつも通りの現実逃避の延長線のものだった。でも、忘年会の一件があって、私用のものから冴島くんにも使ってもらえるように編み直した。
私の行動は正しいのか、編みながらずっと迷っていたけれど、冴島くんの仕草を見たら全てが杞憂だと思えた。
「そうだ。俺もこれあげる」
冴島くんは自分の首から金色のネックレスを取り外した。そして、そのネックレスを私の手の上に乗せてくれた。
「これ、俺が作ったやつ。細田の好みに合うかは分からないけど」
冴島くんが作ったネックレスは、素人が作ったとは思えないほど、精巧なものだった。
「すごく嬉しい。私、ずっと使う」
「はは、大袈裟だよ」
こうして互いの作品を交換し合いながら、私たちは年の瀬が迫る町を歩く
きっと、私と冴島くんが同僚以上の関係に深まることはない。このまま駅に着けば、互いに別の電車に乗って、次に会うのは年明け後だ。
それでも、私は幸せだと思う。
自分の好きなことについて話すのは、楽しいことだ。私はそんな当たり前のことを、今まで知らずに生きて来たのだ。
それは私が自分について語ることを、必要以上に怖がっていたからだ。
でも、今は違う。冴島くんを通して、話すことが楽しいことだと知ることが出来た。
だからもし、冴島くんと『カリキュレーター』について話すことが出来たら、どれだけ嬉しいことだろう。
私のハンドメイドの趣味について冴島くんが笑わずにいてくれるのは、冴島くんも共通の趣味を持っているからだ。
もし私がアイドルオタクをしていると聞いた時、冴島くんはどういう反応をするだろう。
もしかしたら、笑われるかもしれない。
でも、冴島くんならそうはしないと信じられる。
だから、
「あ、あのね、私、今度ライブに行って来るんだ。年明けライブがあってね」
勇気をもって話を切り出すことにした。「へぇ、なんの?」、冴島くんは興味深そうに聞いてくれる。
「カリキュレーターっていう男性アイドルグループ」
私はポケットに入れた手の力が、途端に強くなる。鼓動もやけに速い。
当然だ。私は今までにしたことない話を、これから二回もしなければいけないのだから。
「でね、そのチケットが一席分余ってるんだけど、もしよかったら一緒に行かない?」
足して、引いて、割って、掛けながら歩んで来た私のこれまでの人生は、きっと無駄なことなんて一つもない。
<――終わり>
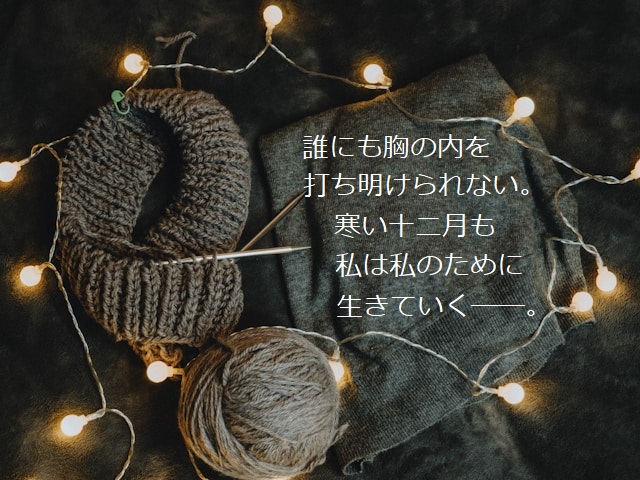


コメント