***
所詮世の中というものは、自分以外の人間は敵だ。
社会に出ると、その言葉がより一層身に染みて分かる。
「一番可愛いのは自分、だもんな」
公園のベンチでスマホゲームに没頭しながら、俺は思い切り溜め息を吐いた。
とある商社の営業マンだった俺は、会社の業績を上げるために、自社の商品を必死に売った。間違いなく自分の足で正当に稼いだものだと言える。会社の売上に貢献した俺は、少しずつ、けれど着実に自分の役職を上げて、出世頭と言われるほどだった。
なのに、
「伊達誠也。お前、虚偽の報告を上げているだろう」
いつも通りに会社に行った途端、信頼していた上司から謂れのない言葉を言われた。突然のことに言葉を失っていると、「ほら、これが証拠だ」と書類を見せられた。その書類には、でたらめな数字が書かれていた。
「これは俺じゃありません」
「そうか? でも、お前がいつも一人で仕事をしているという話を、周りからはよく耳にしていたんだ。一人の時に、虚偽報告の書類でも作っていたんじゃないのか?」
人の意見に耳を傾けることなく、あたかも決めつけたような言い方だった。
そう言われた途端、俺の中で何かが崩れ落ちた。端的に言えば、反論することに対して、どうでもよくなってしまったのだ。
きっと俺が何を言っても、上司は難癖をつけて否定するだろう。
俺が一人で仕事をしていたのは、周りが仕事に対してやる気がなかったからだ。給料を貰って働いているというのに、ギリギリ目標に到達出来るくらいの必要最低限の仕事をこなし、後はサボりにサボる。俺が何度周りに仕事をちゃんとやるように言っても変わることがなかった。
会社のために俺が出来ることをやっていただけだというのに、出る杭として俺は打たれてしまったようだ。
自分の感情に蓋をするようになった俺は、徐々にここで仕事を続ける理由もなくなっていき、ついに退職届を出した。上司に詰め寄られてから、一か月後のことだ。
その時の上司の顔と、周りの人達から滲み出ていた空気が、頭から消えて離れない。
いかにも俺がいなくなって清々した、と言いたげだった。
「……ち」
半ば無意識にいじっていたスマホのゲームの中でさえ敵にやられてしまい、思わず俺は悪態を吐いた。
世の中、敵ばかりだ。
ゲームであれば、敵を倒せばレベルアップする。仮に負けたとしても、命まで奪われることはない。また勝てるまでコンティニューをすればいいだけだ。
しかし、現実は違う。現実で敵にやられれば、メンタルはやられ、生きる希望がなくなっていく。よほどの人間でない限り、現状を打破しようなんていう考えにさえ至らない。
いつの世も、強いのは大多数に所属する人間と、権力を持っている人間だ。
「俺みたいな中途半端な奴が、一番ダメなんだよ」
会社に裏切られたというのに、皮肉にも空は青かった。
前は向けない。真正面には、俺が勤めていた会社が入っているビルがある。今視界に入ってしまえば、逃げるという選択しか取れない自分を惨めに思ってしまうだけだ。
もしも、なんてないけれど、もしも逃げ出さずに自分の居心地が良い会社を作るために努力していたら、どうだっただろう。周りの意見を聞いて、周りと俺の妥協点を探して、互いにとって理想の――、
「ないな」
自分の絵空事に、俺は嘲笑を浮かべた。
結局、人間の本質は変わらない。自分の立場が大切で、よほどの身内出ない限り、無償の愛情なんて注ぐことはしない。仲良くなっても、自分の立場が危うくなったら、手の平を返す。
自分の利益を度外視して、他者のために投資出来る人がいるならば、その人は人の世を離れた聖人だと言えよう。
そんな奇跡の確率を信じたり、周りに変化を期待するよりも、結局は自分がどうにかしなければならないのだ。
「そろそろ帰るか」
ゲームを続けることも億劫になって、俺はベンチから立ち上がった。
俺には会社以外にも居場所はいくつもある。家族だっているし、半年ほど付き合っている彼女だっている。この画面を通じてゲーム仲間だっている。
敵が多いとしても、少なからず信頼出来る人もいる。
そう思えば、また立ち上がってみようという気も湧き上がるというものだ。
八時間という時間の縛りがなくなった今、俺は自由にやりたいことが出来る。もう誰かに気を使いながら生きていかなくてもいいのだ。
<――②へ続く>
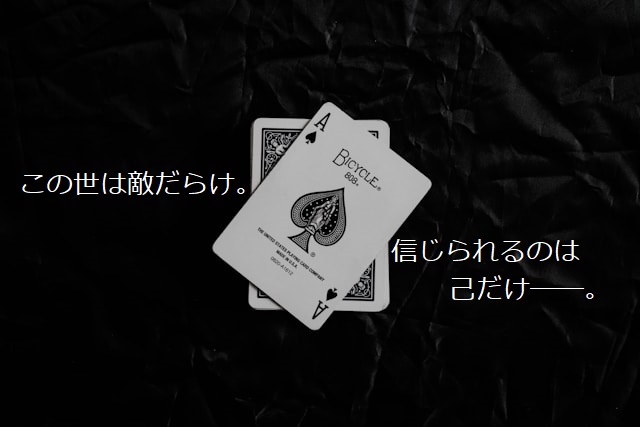


コメント